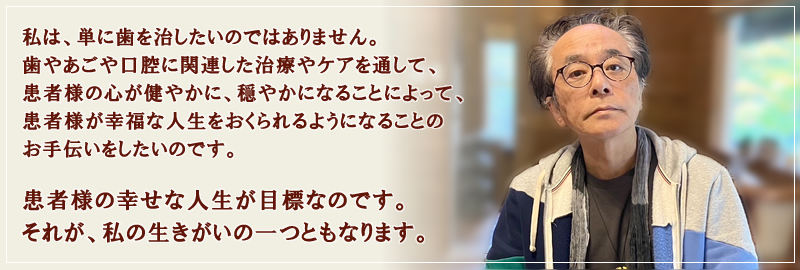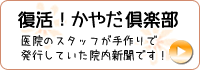読書のお話 その2
|
レアード・ハント、1968年生まれ、現デンヴァー 大学英文科教授作。柴田元幸先生訳の「優しい鬼(Kind One)」は、わたくしの精神状態も影響して、これまでになく読むのに骨が折れ、長時間かかった作品でした。柴田先生もポール・オースターも絶賛のこの作品は、残念ながらわたしには「猫に小判 」、皆目良さの分からない作品でした。柴田先生曰く、「現代のアメリカにおいてもっとも魅力的な声の聞こえる作品を書く作家」なのだそうです。ストーリーはそう複雑ではありません。奴隷制度を核にする作品とまでは思いもよりませんでしたが、散文でありながら「音読に魅力」のある作品は、韻文的で文章がいか様にも解釈でき、いか様にも「さっぱり分からず」、予備知識のないわたくしのような素人には本当のよさの分からない作品でした。この作家の「インディアナ、インディアナ」は柴田先生が訳したもっとも美しい小説の一つらしいので、気を取り直して、再挑戦してみようかなとは思っています。 様々な職を転々としながら本国アメリカでは二流、三流の作家と評され、フランスから評価が高まった(ニューヨーク・タイムズの書評が本国では無名の作家がスタインベックやヘミングウェイと同じように高く評価されているという奇妙な事実を伝えたのが1946年の冬だったそうです)という1897年テネシーで生まれたホレス・マッコイの「彼らは廃馬を撃つ」を読みました。「大恐慌初期の不気味な現象の一つだったダンス・マラソン」で一儲けしようとする、ハリウッドで飢えて堕落していく、映画にとりつかれた男女のみじめな状況を描いた傑作とか。題名の意味が最後まで分からなかったのですが、じぶんが小さな少年であった頃、足を折った馬(廃馬)に情けをかけて撃ち殺した祖父のことが理解できなかったことを思い出した瞬間に、芽の出ないハリウッドで疲れ切って鬱的になりじぶんを撃ち殺してくれというダンスパートナーの願いを迷わずかなえてしまった結末で、やっとその意味を理解したのです。突拍子無く、説明の少ない小説で、それが、かえって理解しがたいハリウッドに狂った若者たちの不安定な気分を現わしているのかも知れませんが、読むのになかなか調子の出ない一冊ではありました。 1882年プラハ生まれのユダヤ系作家レオ・ ペルッツという作家の「聖ペテロの雪」を読みました。ペルッツは18歳でウィーンに移住、ナチスがオーストリアを併合 すると、パレスティナに亡命した作家だそうです。かのボルヘスが愛読したという稀代のストリーテラーだそうです。この作品はドイツの寒村を舞台にした、ある男爵の神聖ローマ帝国の復興を画策する物語ですが、やはり、核となるのは主人公の医師が思慕する既婚の女性との一時の恋が重要なテーマとなる物語でした。権力が、実際にあった騒動を揉み消してしまうという、深く読めば社会批判も籠った作品なのでしょうが、わたしには予備知識が無さ過ぎました。なんとなく、非合理なロシアの寒村を舞台にした作品のような錯覚を覚えながら読み終えました。もう一作読んでみないと、この作家の評価はできないなあ、という中途半端な理解のまま作品を読み終えてしまった感があります。しかし、騒動に巻き込まれながら一命を 取りとめた主人公が、すべての非合理を呑みこんで、一時の恋に落ちた女性を護るために不本意に己を押し殺した返答をする結末は、大人の愛を感じる大団円ではありました。 ミランダ・ジュライ、映画脚本家であり映画監督もこなす映画人の、普通の市井の人々のインタビュー集「あなたを選んでくれるもの」を読みました。机上の空想のなかに生きる映画人の作者は、取るに足らないような些末な人生を生きる人々へのインタビューを通じて、生々しい人生に圧倒され、星の数ほどこの世界に溢れている夥しい濃厚な人生物語の息苦しさに圧倒され、四苦八苦の末に「ザ・フューチャー」という映画を2011年に完成させるに至ったのだそうです。わたしが日々の診療のなかで、息苦しいほどに重々しいそれぞれの人生に圧倒されるのは、やはり障害や難病を背負いながらひた向きに苦悩しながら生きている人々と家族の生き様です。同情や優越感などからではなく、憧憬と感動にみちた勇気を与えてもらえるからです。ミランダもきっとそうだったに違いありません。 刀根里衣(とねさとえ)さんは、1984年生まれの絵本作家。実力を認められてイタリアのミラノを拠点に絵本の製作をされているのだそうです。「ぴっぽのたび」は背景の画の圧倒的な美しさといったら、ありません!! フランスの映画監督、パトリス・ルコントの「いないも同然だった男」を読みました。存在感の全くない主人公は、大統領官邸に平気で入り込んで、なんと大統領の執務室まで覗けるくらい存在感が無く、イスに腰掛けていたら誰もいないと間違えられて、他人が膝の上に座ってしまうというのです。この存在感の無さを執拗に表現するくだりは、ちょっと辟易してしまいましたが、この男が憧れの同僚の娘に恋をして、なんとか自分をアピールするために思いついたのが、ドーバー海峡を独りで泳ぎ切るという突拍子もない行動だったのです。カモメの群れに襲われたり、イルカに援けられたり、 筋肉の痙攣に襲われたり、無事泳ぎ切ってお目当ての娘としっぽり……と思いきや、単なる夢だったり。ドタバタ三流小説に堕しかけたころ、力尽きた男を異国の貨物船が救い、にわか乗組員となって、開き直り、いっぱしの存在感のある海の男になってしまいます。それまでの日常生活の延長のドタバタが、すべての過去を捨てて海の男として生きることにした途端に、骨太い飛躍となります。ひ弱で存在感の無い我われのような人間でも、腹を決めて思い切れば、すべてを投げ出して新たな人生が開けるんだ、と言われているような気持ちになりました。最後は、とうとう憧れの娘にあっと言わせるのですが、そのとき男は、もうその娘への想いを乗り越えていて、―きっと男らしく生き抜いて行くのでしょう。 ここのところずっと、読み応えのある物語りのしっかりした小説に 見離されていたので、やっぱり、ポール・オースターを手に取ってしまったのです。「ミスター・ヴァーティゴ」。最初、なんだこれは! オースターらしくない、波乱万丈なだけの少年の話かと思っていたら、大団円にきて、やっぱりさすがオースターと感じ入ったわけです。少年の独白は、やがて老人の独白となり、人生のむなしさとはかなさに塗り込められた、オースターの世界が広がってきて、人間なんて所詮こんなもんだよ、と……。悲しいからこそ人生。友情あり、師弟愛あり。セックスあり。そして、やがて、悲しき人生あり、みたいな。柴田元幸先生は、これはおとぎ話を愛するオースターらしい、おとぎ話だと書かれておられましたが、人生のむなしさと切なさを知るものだけの書けるオースターらしい、悲しみに満ちた作品ではありました。オースター(というより柴田先生というべきかも知れませんが)は、ちょっとした人生観をちょっとした場面で登場人物に言わせるんですけど、それが例えようもなく真実に満ちているのです。 シェル・シルヴァスタイン(村上春樹訳)の「おおきな木」を読みました。村上春樹も「訳者あとがき」で書いていましたが 、読む人がそれぞれになにかを感じて、じぶんなりに受け取ればいいと思いました。作者は見え透いた母性を賛美している訳ではなかろう、とわたしも思います。折に触れて、人生のさまざまな場面で読み返してみたい「ちいさな本」でした。それが世界38か国で、900万部も読まれている理由なのでしょう。 順天堂大学医学部の病理学の教授 で、がん哲学外来を実践なさっている樋野興夫(ひの・おきお)先生の「明日この世を去るとしても、今日の花に水をあげなさい」を読みました。2008年に先生が始められた「がん哲学外来」は注目されて、いまでは全国80か所で広がりをみせているそうです。「暇気な風貌」(現在の大病院での治療では、医者は患者さんの顔をじっくり見る余裕さえないために、パソコンの画面ばかり見ている、と樋野先生は患者さんもお医者さんも不本意だろうと考えられていて、「暇気な風貌」は実は非常に大切な意味があるのです)で、無償で30分から1時間のゆったりとした時間をとってなされる「哲学外来」は、「偉大なるお節介」精神で、患者さんの悩みや不安をじっくり聞いて、有効で副作用の全くない「言葉の処方箋」を出されるのだそうです。患者さんは、みなさんにこにこされて「哲学外来」を後にされるそうで、効き目は抜群のようです。先生は、「命より大切なものはない。命が一番大事」とは、考えない方がいいと言われます。「命がなによりも大切」と考えてしまうと、死はネガティブなもの、命の敵になってしまって、死におびえて生きることになってしまう。命はとても尊いものだけれど、「自分の命よりも大切なものがある」と思った方が、幸せな人生を送ることができるようだ、と。わたくしたち一人ひとりには与えられた役割や使命があると言われます。難しく考えなくてもいいそうです。家族に優しくつくしたり、周囲の人を和やかにしたり元気にしたりすることかもしれません。困っている人の手助けをすることかも、あるいは世界を変えるような重大な使命を成し遂げることかもしれません。人それぞれだと……。この本は、なにかもやもやと不安に駆られながら生きているわたしたち現代人に、ある気づきを与えてくれる本だと思いました。シンプルだけれど、とても示唆に富む重要なことが行間に書かれた本でした。 わたしがどういった経緯でこの文庫を手にしたのかは定かではありませんが、ハンナ・ケントという1985年、オーストラリア生まれの若い女性のものした「凍える墓」を読みました。アイルランド最後の死刑囚の女性を描いた作品で、たくさんの文学賞を受賞して、映画にもなった(?、これからなる??)話題作です。瀕死の人間の苦しみを早く終わらせてあげることが犯罪かどうか、批難されるべきことかどうか は、時と場合で評価は違う難しい問題ではあります。切腹する人の介錯は大切な役目だったでしょうし、歴史上も、戦時中や巷でも、そのような苦渋の役割はあったことでしょう。しかし、これが医療の現場でとなると、これはまた大変に難しい問題を孕んだ命題になってしまいます。このお話は、19世紀の初めにアイスランドで実際にあった事件と死刑執行をテーマにしています。男女の愛憎の入り乱れた複雑な状況で、「とどめをさす」行為が犯罪かどうか!? 犯罪でないとしたら、このアイルランド最後の死刑囚とされている女性の事件は、冤罪なのかも知れません。長いあいだ死刑の執行を待ち、いよいよ執行が目前に迫った状況の描写は凄まじく、厳粛でしたが、病や老衰の往生際で死を待たねばならない人々は、古今東西ずーっといるわけで、けして遠い昔のお話という訳ではないと思いました。 童話もれっきとした読書、でしょうか? 「いもとようこ」さんの「ずっとそばに・・・」を読みました。里に下りて行って人間に捕まり、帰ってこなかったおとうさんとおかあさんを持つ「くまさん」は、リスやウサギ、キツネ、タヌキなどのひとりぼっちのこどもたちを、じぶんのこのように せわをし、ねるときも だっこして、けっしてひとりぼっちには させません。ひとりぼっちの さみしさを だれよりも よく しっていたからです。やまの きのみが まったくならなかった あるふゆをまえにしたひに くまさんは けっしんして やまをおり、ひとざとでかきのみを 「すこしだけ いただいた」のですが、みつかり あしを じゅうでうたれてしまいます。 よわっていく くまさんに すがりついて こどもたちは 「こんどは ぼくらが ずっと そばにいるよ」。「こんどは ぼくたちが あたためてあげる」。くまさんと こどもたちの うえに ゆきがふってきて、ふりつもります。やがて しろい おやまになって。ゆきは ますます はげしく ふりつづけます。 かみさま、 どうか このこたちを おまもりください・・・・・・ わたしの大好きな望月通陽(もちづき・みちあき)さんの装画に誘われ、「薔薇とハナムグリ」という愉快そうな題名についふらふらと買ってしまったのが、光文社古典新訳文庫の本書だったのです。作者のアルベルト・モラヴィアは20世紀イタリアを代表する小説家の一人だそうです。このシュルレアリスム・風刺短篇集という副題は、わたしには新鮮でしたが、内容は昔読んだ星 新一のショートショートのように、わたしのこころの琴線には触れることなく、まるで手からこぼれ落ちる砂のように、過ぎ去ってしまいました。猫に小判というやつなのでしょう。わたしには、まだ、シュルレアリスムの何たるかを理解するこころの準備ができていないようです。 やれやれ・・・・・・。 ホセ・ドノソ の「境界なき土地」を読みました。マリオ・バルガス・リョサは大絶賛の作品らしいのですが、日常を描けば、そのまま異常な錯綜した世界を描くことになる(??わたしの勝手な根も葉もない偏見ですが)南米の文学は、大好きですが、初めて読んだドノソは、「またかよ」といった感じでした。ドノソお前もか! みたいな。でも、ラテンアメリカの代表的作家らしいので、また、いつか他の作品を、できれば代表作である「夜のみだらな鳥」を読むまで、この作家のじぶんの中における評価は保留しておこうと思います。リョサに、「ドノソの人生そのものが文学だった」と言わせた人らしいですので……。 「詩と死をむすぶもの 詩人と医師の往復書簡」(文庫版)は谷川俊太郎とホスピスで終末医療専門の病院を運営する医師、徳永 進先生の往復書簡です。「はじめに」のなかで、徳永先生は書かれます。「老いた人の死と若い人の死、違わない。信仰に支えられ死を受け容れた人と、『くやしい』と叫びながら世を去る人、違わない。温かい家族に取り囲まれて亡くなる人と、人一人いない病室で亡くなる人、違わない。生きていること、死ぬこと、うーん、違わない。ちいさなことはたくさん違うが、一番大切なことは、違わない。みな同じ。」と。そのことばを必死で理解しようと本書を読み進めましたが、残念ながらわたくしのような凡人には、その答えは未だみつかりません。これからも、この本をずっと読み込んで、探そうと思います。わたくしはさすが詩人、谷川と思って読んでいたら、わたくしの唯一無二の親友(四国の高校の国語の教師で、谷川もよく読んでいるとか。ちょっと、変わった人間です。随分変わっているかな!?)は、徳永先生にはとても親しみを感じて、谷川には厳しい感想を述べました。同業者だからかな? 谷川をよく知っているからかな? そう言われれば、だんだん、徳永先生のことばの重みがずんずんと、いや、もっと軽やかにひらひらと軽妙に意味深になっていきます。たくさんの内容のなかで印象的なのは、エリザベス・キューブラー・ロス―死にゆく人々を励まし、人には死を受け容れる力があると画期的な考えを提言したり、実践した、超悟りに近い人間―が、じぶんに病を得て、みんなから見捨てられるような姿になって、テレビカメラに向かって怒りをぶちまけている姿を見た、徳永先生は、「すごくよかった。こりゃあ本物だ、と思いました。ぼくは思わずにっこり笑いました。もう一人のマザー・テレサ、とも思いました……」。「思い通りの人生なんて、どこか嘘嘘しい。人間なんて誰だってそんなに違わない。たいして違わない。矛盾だらけが本来なのだと」。やはり、友人が言うように、徳永先生はすごいのかも知れません。 辰巳芳子さんの「食に生きて 私が大切に思うこと」を読みました。前半は、はっきり申しますと退屈していたのですが、そこにもこんなことが書かれてありました。「男には小松菜のおひたしなんて、女子供用の野菜のおひたし食べさせちゃダメ、。男の食べるおひたしは必ず根三つ葉とか芹とか、香りのあるものでなきゃいけない。男ってものは、晩御飯ともなれば、いきなり素面で、焼き魚で白いご飯なんてことはあり得ない。まず、唐墨とか、このわたとか、そういう珍味でとりあえず、一杯やる。それでいい心持ちになったら、それから主菜でしょう。・・・・・・」男尊女卑で、どこやらの団体からか叱られそうですが、90歳のおばあさんがおっしゃられていることですから、年齢にと時代の価値観に免じて、お許しいただきたい。 辰巳さん、日本で初めて生ハムを作られた料理研究家(?)として有名なのだそうです。終章の食に関するお話になると、いきなり凄い! ある全日本のサッカーの監督をされた人が言ったそうです。「日本選手に足らないところは、試合に向けて何を食べたらいいかを知らないことだ」とか。90分間走り続けてくたびれず、闘争心も途切れないためには、何より動物の栄養とか筋の栄養とか、骨の栄養まで余すところ無く動物を食べ尽くす、外国の食べ方に習わないといけない、と。ロースだとかヒレだとか、日本の肉屋で売っているひらひらの薄ぺっらな肉以外の動物の力をどう摂取するか! 「ヒトが人になるための条件はいろいろあるけど、欠ければ取り返しのつかない条件の一つが「食」である。いのち(神仏)の慈悲から目をそらさず、愛し愛されることを存在の核に据え、宇宙・地球、すなわち風土と一つになり、その一環を生きること。「食べ物」をつくり、「食す」ということはこの在り方を尊厳すること! コロラド州のデンヴァー大学の教授であったジョン・ウィリアムズの手になる「ストーナー」が米国ではじめて刊行されたのは、1965年のことだそうです。当時しかるべき評価ののちその存在の忘れ去られていた本作品は、2006年にニューヨークの出版社で復刊され、まず、フランスでベセトセラーとなり、ヨーロッパ中で熱烈な歓迎を受け、 多くの国で話題となっていったそうです。貧しい農家に生まれたストーナーは、大学で英文学と出会い、一生を一大学教師として、さまざまな苦難に見舞われながら、黙々と、ひたむきに生き抜いたのです。大きな挫折の後に、幸福な時間におずおずと手を伸ばし、慈しみ、一時の眩いばかりの輝きの中に生きる時間もあったのです。なんと美しく、静かな共感を呼び起こす小説でしょう。「ストーナー」に描かれる悲しみは、「文学的な悲しみではなく、もっと純粋な、人が生きていくうえで味わう真の悲しみに近い……」。この翻訳を手がけた東江一紀は、癌との闘病をしながら、本書を和訳し、臨終には家族と口述筆記をしながら、残り一ページを残して力尽き、翌日に息を引き取ったそうです。そのあとを託された布施由紀子氏は、「人は誰しも、思うにまかせない人生を懸命に生きている。人がひとり生きるということは、それ自体がすごいことなのだ。非凡も平凡もない。がんばれよと、この小説を通じて著者と訳者に励まされるような気持ちになる」と書いています。人生では、その一生を左右する大切な人との出会いがありますが、生きる意味を示唆してくれる美しい本との出会いも、それに負けず劣らず、人の人生に大きな影響を与えてくれます。この作品との出会いは、まさにそういう希少な出会いでした。「読んでいると、さざ波のようにひたひたと悲しみの寄せてくる」小説でした。ストーナーが最後に息を引き取る瞬間を読みながら、わたしのからだのなかの何か一部も、共鳴しながら共に死にゆくのだ、という錯覚を覚え、恐ろしくすらあったのは事実でした。 小野正嗣の「九年前の祈り」を読みました。豊後水道を挟んで、この作品の舞台と作家の出身地はわたしの四国の出生地と向かい合っているに違いないと思います。4つの連作小品は重なり合い、繋がり合いながら、書かれている。誰かの「田園の憂鬱」ではないけれど、僻地に住む者のうら悲しさは、よく理解できるが故に、しょうゆ臭いようで 鼻について仕方なかったのです。なかでは、「お見舞い」を好ましく読みました。寒村には珍しく東京の大学にまで 進学しながら、家族を失い酒に溺れてしまった主人公の先輩(友人)。小さな頃から動作が鈍く、不器用で、勉強もできず皆から疎まれていた同級生の伽(トギ=友人)が、成人してからも寒村で独身を通し町のゴミ処理場で働き、ついには脳腫瘍で人知れず入院する。主人公はそのような軽んじられるような人生から、目を離すことができない。物寂し過ぎるのは、実は日本の片田舎(僻地)の常態なのです。その実態を小さな頃に体験してきたわたしにとって、この作家の眼差しは近し過ぎて、辟易するのです。朝日新人文学賞、三島由紀夫賞、そして、今回の芥川賞と、受賞歴はこの作家の実力を間違いなく証明してはいますが……。 フランス人作家パトリック・モディアノ の「イヴォンヌの香り」を読みました。原題は「哀しみの館」だそうです。やはり、そのほうがぴったりしていると思います。フランスがアルジェリア独立戦争の最中にあった時代に、おそらく兵役を逃れてスイスとの国境に近い片田舎で不安な日々を過ごす青年の、行きずりの恋のような、美しいけれどなにかうらぶれた翳をにおわせる美女イヴォンヌとの逢瀬を綴った作品でした。物語はその青年が12年後に回想するような仕立て手で、失われた過去を遡って時の流れをむなしく実感するという主題はこの作家の十八番なのだそうです。この作品は、鄙びた片田舎のちょっと高級なホテルやダンスホールに夜な夜な出没するブルジョアジーの世界を描いていて、わたしには興味のない世界でしたから、初めて読むこの作家の作品としては、ハズレでした。ですが、根無し草のような翳りのある人物や、何かしら不安にとりつかれ、人目を忍んで脱出の機を伺うような人物ばかりを描くと評されていたこの作家の作風には、共感を覚えますので、もう2,3作は読んでみたいと考えています。じぶんの好まない作家だと決めつけるには、2014年ノーベル賞作家という冠はやはり惜しい気もします・・・・・・。ちなみに、ノーベル賞受賞理由として、その作品が「記憶の芸術」と評価され、「現代のマルセル・プルースト」だとも評されたのだそうです。 平野啓一郎「透明な迷宮」を読みました。つい手に取ってしまう日本人作家の一人です。この作家は頭脳明晰なんでしょうね。作品が寓意に満ちていて、設計が意図的であると思います。本作は、狂気にすれすれの人物が 沢山出てきたように思います。潤沢な知識と、書く目的がはっきりしているのが、限界と言えば限界のようにも思いますが、やはり深遠なものを持っています。けれど、作家の中で答えが既に出てしまっているような、やるせなさを感じるのはわたしだけでしょうか? きっと、もっと大きな意図をもっているんだろうが、どうしても追いついていけないような、もどかしさです。薄学の故です。この人も、執拗な三島由紀夫ファンなんだろうな、と思いながら読みました。深くは読んでいないかも知れませんが、若い作家らしい挑戦に満ちていることは、この作家が将来もっと大きくなっていく妨げにはならないような気がしています。 「ディア・ライフ」アリス・マンローを読みました。以前の「読書のお話」(マンローが2013年のノーベル賞受賞者と決まった頃に書いた)で、マンローの作品はメッセージ性が低いというようなことを書いてしまいました。私の感想だから、それはそれでいいのですが、今回の作品はマンローが“一応”最後の作品集としてノーベル賞受賞の前年に出版(日本ではノーベル賞をもらったその年に出版)された作品ですから、ノーベル賞受賞についてのたくさんの方々の賞賛の声が「訳者あとがき」にありました。「ノーベル文学賞はともすると政治的姿勢を明確にしている作家に与えられる傾向にあるが、マンローの受賞は文学的価値のみによって決定されたものだ」と。「これまで『家庭』はキャンパスとしては小さすぎ、本当に素晴らしいものは描けないとみなされてきたが、今回の受賞は家庭生活を描いた物語の価値を認めたものだ」と、アメリカのある作家が評したそうです。短編の女王と呼ばれるマンローの作品を読んでいると、本当に疲れます。それは、短編でありながら、内容的には長編小説にも劣らないような広がりがあり、複雑で、人の心の襞や複雑さ、不可解さを丹念に描いているからだと思います。適当な長さの「掌の小説」をゆっくり読んだというよりは、短いけれど「ちゃんとした小説」群を読み終わったという疲れ方をします。マンロー自身も「短編は長編小説の習作みたいに思われている」ようなことを不満げに語ったというような記載もありました。なにより、短編を完成させるにあたって、マンローが「毎日勤勉に書き、一篇に2,3ヶ月、どうかすると7,8ヶ月もかけて、書いては書き直し」、推敲に推敲を重ねる作家だと知りました。マンローを読むのは疲れるのも当然のように思いました。私が彼女の作品を読み続けてきた理由が、分かったような気がしました。今回の作品も、80歳を越えた大人だからこそ書けるような作品がたくさんありました。「メッセージ性が低い」という私の感想は、ことばとしては大変不適切なものですが、アリス・マンローという作家の作品の「大切な一面」を、図らずも 言い当てているような気もするのですが、いかがでしょうか!? ポール・オースター(柴田元幸先生訳)は、安心して(?)読める私のお気に入りの作家です。「安心して 」というのは、誤解を生む言い方で、ただ連作を多く読んでいて、「慣れている」作家というような意味です。この人が、「物語中物語」を得意とする稀代のストーリーテラーであることに疑問を差し挟む余地はありません。トルコ初のノーベル賞作家のオルハン・パムクも太鼓判を押していますから。この人の和訳最新作「闇の中の男」を読みました。ストーリーが命の作家ですから、その粗筋を辿るような野暮は止めておきますが、体の不自由な老人が最愛の亡き妻を回顧するくだりは、真実の光を放って秀逸です。曰く、「神々に悪戯を仕掛けられて、私が本当の恋に落ちる運命の女の子、私の人生に意味を与えるために生まれてきたたった一人の人物」。曰く、「自分が他人に及ぼす影響もわかっていなかった。自分が引き起こしうる傷も、私を愛してくれる人たちに自分が与えうる痛みもわからなかった。〇〇は私の大地であり、世界との唯一確かなつながりだった。彼女と一緒にいることで、実際よりいい人間に、より健全でより強くてより正気の人間になることができた」! 「損なわれた部分が全体に障害をもたらして、精神や心の構造」に問題を抱えている私という人間を、「正気の 」人間たらしめてくれている私の最愛の妻に、そっくりそのまま、このオースターのことばを贈りたいと思うのです。 ガルシア・マルケスの講演集「ぼくはスピーチをするために来たのではありません」は、ちょっと退屈な本でしたが、この人の大切にしていることを知ることはできました。それに、無類のスピーチ嫌いだといういうのは、好感がもてました。本書で紹介されていていた、現代ラテンアメリカ文学を先導したフリオ・コルタサルという作家を知ることもできました。マルケスの親友であったようですが、「公的な場に出ると、なるべく目立たないようにいつも一歩後ろに下がっていながら、ひとびとに敬意や賞賛の念や、愛情や崇拝の念まで抱かせる」魅力的な作家だったようで、代表作の「もう一つの空」をぜひ読んでみたくなりました。それと、わたくしの次男が生まれた日が、1969年にニール・アームストロングが月面に降り立った日と同じ月日であったことも初めて知ったのです。追伸。パヴェーゼの自死について、自死一般について、わたくしが非難した前回の「読書のお話」のことで、わたくしの知る女性は、「ひとが自死を選ぶとき、一般のひととは全く違ったベールに包まれたような世界観や価値観で、世の中や人生を眺めて決めることだから、安易に一般的な論理で(実はわたくしが「自死」を忌避したのは、論理ではなかったのですが)批難すべきでない」というようなことを、言いました。それも、本当の事だと思います。前回、わたしが文章を書いていた時の心境が、まさに、自死を否定したい状況であったのです。ただ、生きたくても病で長く生きられないひとびともいるのだということを恨めしく思う、裏返しの気持ちから書いたものです。「自死」を選んだひとたちを蔑む気持ちなど毛頭ありません。(詳しくは、末井 昭「自殺」についての、わたくしの読後感をお読みください) パヴェーゼの「月と篝火」は、なんと読むのに時間も掛かり、苦心惨憺して読んだ本であったことか。 私事も重なり、この本を読むには、一か月以上を費やしたと思います。この人の「美しき夏」は読んだような?? 本作は、彼の長編小説としては遺作になります。42,3歳で自死したのです。強すぎる感受性は、往々にして自死に繋がりますが、現在のわたしからみれば、そんなことで自死せねばならない人間は、酷な言い方をすれば、身勝手もいいところだと思います。芸術家の自死は、ある意味必然性を帯びた、仕方のない帰結ですが、今のわたしには、「なんと恐れ多い、不遜で、卑怯な行為か!」、命を与えてくれた親は、どんなにか苦しむことか、どんなにか救われぬ事か! 命を粗末にすることに、大義など無い!というのが、偽らざる気持ちです。親にいただいた命を粗末にしてはいけません。死ぬくらいなら、死ぬほど苦しみぬいてでもで生きぬいて欲しいのです! 生きたくても、死を受け入れざるをえない人は、世に多いのです。 吉田篤弘の「木挽町月光夜咄(こびきちょうげっこうよばなし)」 を読みました。この作家は、わたしが連作を読む数少ない日本人作家の一人です。この人の本は、なんか魅かれるんですが、読んでいると、大抵飽きてきて、でも、気が付くとまた本を買っているのです。この本はエッセイだから、なをのこと大義かったのですが、素の吉田篤弘を知ることができてよかったです。「子供のときからなぜか舞台袖が好ましい」「夏の夕方の神宮球場のまわりを歩いていると気分がよくなってくる(球場からの照明があふれ、歓声や、球を打つ音が聞こえる。≪舞台のはずれなんですね≫)」「映画館のロビーや廊下が、ああ、じぶんの居場所なんだと思う」らしいです。華やかな場所の、袖が居心地良いんですね。変な人です。「さみしくない本は、もとより本ではないし、さみしくないなら、本など読む必要もない」などと嘯く御仁、だから、やっぱりつい、退屈だと思いながら読んでしまうんです。「つむじ風食堂の夜」「空ばかり見ていた」「それからはスープのことばかり考えて暮らした」なんか、なんとなく読んでしまったんですよね。 「世界を回せ 下巻 」読了。上巻に続いて、さらにさまざまな人々が、小さな(その人にとってはけっして小さくはありませんが)悩みや苦痛を抱え込みながら、日々を過ごしています。その人々が、どこかで繋がっている。それぞれの人物が演じる役割は本当にささやかでも、そのちっぽけな人々が、世界を回しているのです。そのきっかけの一つである、世界貿易センターのツインタワーを綱渡りするというちょっとした事件は、本当にあった事実だそうです。その27年後に二機のジェット旅客機がそのビルに突っ込み、ビルは崩れ落ち、3000人近い人命が奪われようとは・・・・・・。ニューヨークの最下層に生きる娼婦たちと、その地獄のような生活を無償の愛で支えようとした若き修道士の印象は、特別のものでした。作者にとっても、思い入れの強い登場人物であるに違いありません。作者はその若者と自分をだぶらせていますから。同じアイルランド出身の若者として。その修道士に、神を裏切る行為だと知りつつ、荒がいきれない切ない恋があったことは、救いでもあり、同時に、それが故に、あとに残された年若い女性の魂に焼き付くように残された若き修道士のからだの温もりは、あまりにも残酷ではあります。その若い女性が、修道士との逢瀬を昇華させようとすばするほど、わたしのように齢を重ねて来た者には、なおさら哀れに思われてならないのです。 コラム・マッキャンというアイルランド生まれで米国在住の作家(1965年生まれ)の 「世界を回せ 上」を読みました。上巻だけでここに感想を書きたいと思ったのは、それだけ素晴らしい作品だと思ったからですし、上巻だけ読んでも(下巻がますます楽しみなのも事実ですが)満足できるような作品だったからです。この作品、2009年の全米図書賞を受賞、2011年には国際IMPAダブリン文学賞を受けています。マッキャンはダブリンの生まれです。1974年の夏の朝、ニューヨークで、一人の若者が世界貿易センターのツインタワーの間で綱渡りを始めます。初め、人が宙に浮かんでいるように見える。それを、見上げる通勤の人々は騒然となります。秘かに、その人物が落下するのを内心期待したりしながら……。ブロンクスの娼婦たちに献身的に尽くすアイルランド出身の若き修道士と、その運転中、追突されての突然の事故死。ベトナム戦争で息子を亡くした母親たちの集い。そのうちの一人が、集いに向かう途中の船上で、綱渡りの若者を目にして、ベトナムで戦死した息子ではないかという想いに囚われます。修道士のバンに追突した芸術家カップルのうちの女性は、現場から逃げ去ったことに罪悪感を持ち続け、そのことを悔いながら、吸い寄せられようにして、死んだ修道士の兄のもとを訪れます。耐えきれない悲劇に直面し、深い悲しみの中にある人々の人生が、繋がっていきます。みな、じぶんを裏切らないように迷い、懸命に生きながら……。慈しみに満ちながら……。綱渡りをしているのは、誰なのか? どのように、人々の人生が回っていくのか? 下巻が楽しみです。 歳のせいか、「読書のお話」にもっとたくさんの本のお話を書いたような、それが、あまりに多くなり過ぎて末尾の古い記載が、しぜんと削除されているような、曖昧な記憶があります。曖昧なのが情けない。いずれにしても、知らず知らず多くを失わないためにも、「読書のお話 その2」を作ります。 |