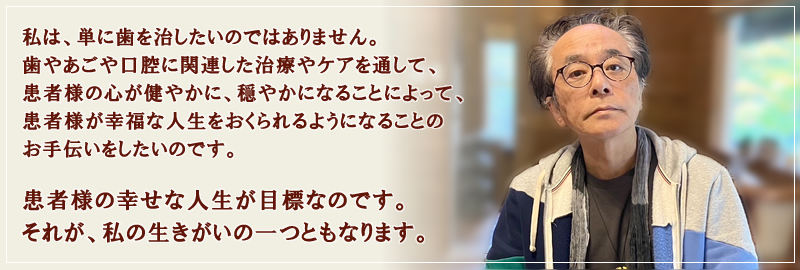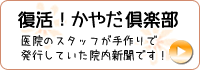読書のお話 その3
|
気が付いてみれば、「読書のお話 その2」は、最初の「読書のお話」を越えて長くなってしまっておりました。そこで、新たに「読書のお話 その3」を設けさせていただきます。お付き合いのほど、よろしくお願い致します(平成28年1月24日)。 新しい読書が上にくるように変更します(平成28年10月16日)。 2000年に新人作家としては極めて異例なピュリツァー受賞で鮮烈なデビューを飾ったジュンパ・ラヒリというインド系女性作家の「停電の夜に」という短編集を読みました。またインドかと、どこがピュリツアー賞なんだと、退屈しながら本当に時間のかかった読書(最近は多い。当たり前になってしまいました)でしたが、最後まで読み切って本当に良かった。訳者の小川高義さんの「訳者あとがき」の言葉が無くても、一押しは最後の作品でした。久しぶりに本を読んで泣きました。デンヴァー大学の教授だったジョン・ウイリアムズの佳作「ストーナー」の読後感に通ずるものがありました。どこの国でだって、堅物で融通の利かない武骨な普通の人生をまじめに生ききった人間に賞賛を惜しむことはないのだと、ほっと嬉しくなってしまいました。この小品を読むためだけにこの本を手に取ってよかったという思いにさせられました。さすがは有名な文学賞をものした作家だと、納得させられた小品ではありました。 国立がんセンター病院長、総長を務められた垣添忠生先生の10年ほど前の著者「 妻を看取る日」を読みました。先生はあの杉村 隆の愛弟子。まさに日本のがん研究のトップにまで上り詰められたがんの超専門家であります。その先生が奥様をがんで亡くされたときに、自死すら考えたと言われながら著されたのがこの本です。その内容については何も言わず先生が書かれたこの文章だけを記します。「……あんな形で姿を現すのは、妻の化身としか考えられなかった。頭の片隅では勝手な思い込みだとわかってはいるが、私は実際に励まされたのだ。葬儀の弔辞で、しばしば「天国から見守ってください」という言葉を耳にする。……あの言葉はその通りなのだと思う。妻がどこか上のほうから私を見守ってくれている感覚が、確かにある。……どんなに非科学的な話であっても、当事者には特別な意味を持っているのである」 韓国の作家、ハン・ガンの「すべての、白いものたち」を読みました。韓国の作家の作品には理由のない無関心を貫いてきましたが、この作家は研ぎ澄まされた感受性とことばの正確で繊細な選択力をもった稀有な作家であるということは、数ページ読んだだけで感じました。全編が悲しみや慈しみ女性ならではの感受性で著されていて、久しぶりにゆっくり時間をかけて終わらないように読みたいという気分にさせられた作品でした。本作は詩のようなえりすぐられた言葉で、言葉少なに書かれたものでしたので、しっかり書き込まれた小説をぜひ読んでみたいという気持ちにさせられた作家ではありました。将来の大器の確約された作家に違いありません。 映画関係者で作家もこなすミランダ・ジュライの作品「最初の悪い男」は、「あなたを選んでくれるもの」をいつか読んで、わたしにとってこの作家の読書二作目となる、初の長編小説でした。まさかこの登場人物が、レズビアンとして主人公の相手役になろうとは思いもよらず、例によって長くかかった読書でした。小説の内容がどうのこうのという以前に、映画関係者らしく読んでいて映像が目に浮かんでくる作品でした。内容も小説の価値観より先に映像としての鮮明さが優先されるような気がして読んでいました。内容的にはハチャメチャで、別に何が言いたかった作品というよりは、見ていての面白さを追求したような作品のように感じました。確かに映画になれば面白そうな作品ではありました。 フランソワーズ ・シュワッブの編集によるフランスで著名な哲学と音楽を深く洞察したヴラジミール・ジャンケレビッチの対談集「死とはなにか」を読みました。一等最初に、この本の訳者である原 章二先生が「訳者あとがき」で、ジャンケレビッチと同時代を生きた小林秀雄が「無常といふ事」と題するエッセイで述べていると示されたことを紹介します。小林曰く「生きている人間はどうしようもない代物で、せいぜい人間になりつつある動物というところかな。死んでしまった人間こそが、まさに人間の形をしている」と。原先生は、「本物」の人間の姿は、どうしようもない「代物」があるからこそ存在するのであり、私たちは人間の死によって、人間の生の姿を見ているのであって、端的にひとの死を目にする時ですら、私たちの見ているものは、そのひとの凝縮された生の形にほかならない、と述べておられます。ジャンケレビッチは死とは人間にとって説明のできない、思考不能の何かだと言います。たぶん、その内容は大変に単純な何かです。しかし、私たちはそれが何であるかはまったく思いつくことができません。それはまったく別の次元のものなのです、と。死は生に立ちはだかり、生を限界づけます。いつの日か死は生を断ち切る。しかし同時に、私たちは知っています、死がなければ人間が人間でさえないことを。大いなる生には死がつねに影のように従い、生に熱と光と力とを与えることを。それゆえ、死なないものは生きない、といえるでしょう。意識が肉体を離れて存在するということも確かでなければ、肉体とともに無に帰すということも確かではありません。死は生を無意味にすることによって生に意味を与えるのです。死は生に意味を与える無意味なのです。短い、しかし真の生涯、愛に満ちた生涯を過ごすか、さもなくば愛を知らない、しかしどこまでも続く生、生とはいえないような生、永遠の死のような生を生きるか、どちらかとしたら、カゲロウのように、ただ半日だけであっても生きたほうがいい、とみなが言うでしょう。そしてこのとき、もう長いも短いもないのです。このとき、私たちはすくなくとも「生きた」と言えるのです。たとえそれを失わなくてはならないにせよ、いや失わなくてはならないがゆえに、私たちは生きたといえるのです。 1940年に南アフリカのケープタウンでオランダ系入植者の末裔として生まれ、英語で書くノーベル賞作家として知られるJ.M.クッツェーの短編連作「モラルの話」を読みました。この作品は英語で書かれながら、まずスペイン語と日本語で読者に手渡されることになった作品です。2018年の5月に日本語の初版が発行されています。この作家がこれまで書いてきた作品群から「いま」伝えておきたい重要項目を選び抜いた宝石箱のような本がこの「モラルの話」なのだそうです。それぞれの短編には現代人のモラルを問うような問題意識が読み取れましたが、全体としてはもっと秩序だった、知識に富む内容を凝縮した作品なのでしょうが、わたくしにはまたしても猫に小判、消化不良の作品でした。なかなか手ごわい作家である母親との 息子を設定した短編は読みごたえはありましたが、やはりわたくしの知識や集中力の不足が如実となった作品ではありました。 藤岡洋子「手のひらの音符」を読みました。とにかくよい小説だという書評に、フラフラと引き寄せられて読んだ作品でした。それぞれに、さまざまな苦悩を抱えた若者たちが 真摯に懸命に、じぶんに正直に生きている生きざまを描いた恋愛小説でしょうか。その生きざまが、さて報われるのか、夢破れるのか。そんな陳腐な興味には作品は応えてくれはしません(当たり前だ)。それに答えを提示するような作品なら、よい小説として評される訳がありません。「この世の中では、なにを悲しむかということは、すこしも問題ではなく、どれだけふかく悲しむか、ということだけが問題なのです」(エーリッヒ・ケストナー「空飛ぶ教室」)人は、それぞれに、皆が違った悲しみを抱えながら生きているのだということを、その悲しみの深さも比べようがない、と無理なく届けてくれた作品としては意味のある作品と言えるのではないでしょうか。 音楽学者、作曲家、指揮者、画家、そして漫画家と多彩な顔をもつ鬼才として知られる(のだそうです。わたくしは存じ上げませんでしたが)フェデリーコ・マリア・サルデリッチが書いた「失われた手稿譜 ヴィヴァルディをめぐる物語」を読みました。この作家の新しい顔としての小説家の評価はイタリアではとても高っかったようです。バロック後期の作曲家の ヴィヴァルディは司祭という聖職者であったことを本書で初めて知りました。晩年は生活苦から借金を重ね、ヴェネツィアを離れ、仕事を求めて向かったウィーンの地で不遇な最期を遂げたそうです。残された膨大な自筆楽譜の数々。兄の魂そのものである手稿譜を守ろうとする弟、手稿譜に純粋な関心を寄せる愛書家の貴族、手稿譜を買い叩こうとする欲にくらんだ司祭、遺産相続でもめる貴族たち、ユダヤ人の音楽学者や果てはムッソリーニまで、さまざまな人々の愛憎、欲望、無知などが複雑に絡み合って、楽譜は手から手へと数奇な運命を辿ります。まるで、オペラの場面展開を見るようなミステリアスな物語は史実を忠実に追ったものだそうです。事実は小説より奇なりという読書案内にほだされて手にした本でしたが、史実の複雑さに関する知識の乏しい者にはその価値が猫に小判のような作品ではありました。予備知識をもった音楽好きが読み込むともっともっとスリリングに興奮して読まれる作品なのだろうという情けない感想を記すよりほかありません。 1896年ポーランドに生まれた画家、美術評論家、エッセイストであるジョゼフ・チャブスキの「収容所のプルースト」を読みました。1939年にソ連軍の捕虜となった著者が収容所でおこなったプルーストの「失われた時を求めて」をめぐる講義の記録です。まず、この先生きることが確約されていない状況にあっても人は知的な充足を求めて生き抜こうとする事実に 人間の希望が見えてきます。著者だけでなくさまざまな講師がお得意の分野の講義をしたのだそうです。真実の探求という文学の行為が、「パンのみで生きるのではない」人間の一つの救いとなることが、戦争という非常時の状況から浮かび上がってきます。講義曰く、真実の探求にのめり込むプルーストは死を恐れなくなっていきます。真実は死によって規定される人生の長さとは無関係に存在するからです。なんらかの衝撃によって人が時間の外側に飛び出したとき、人は死のない真実の瞬間に触れるのだといいます。その作品群の最初から最後まで、神と不死というたった一つの問題に取り憑かれたれた偉大なもう一人の作家がドストエフスキーだそうです。「カラマーゾフの兄弟」を読みたいという、いや、読まねばならないという気持ちになってきました。 コルソン・ホワイトヘッドの「地下鉄道」を読みました。2016年に出版されて以来、その年アメリカで最も熱狂的に読まれ、ピュリッツアァー 賞、全米図書賞などの賞を総なめにし、オバマ大統領の夏の読書リストににも選ばれたり、長く話題作となっているそうです。アメリカで1860年に南北戦争が勃発し、奴隷制に反対する北軍が勝利して、奴隷制が廃止される以前30年ほどのアメリカの奴隷黒人少女が主人公の物語です。史実に敢えて途方もない地下鉄道という虚構を放り込んで成功した作品とされています。奴隷の呪縛から逃れようと命がけの賭けに出た少女の運命をめぐる物語は、そのほとんどが歴史上現実に起こり得たおぞましい出来事であることが、改めてわたくしたちを震え上がらせます。人間の人生にはどのような不幸や試練も起こり得るのだ。それに立ち向かう勇気はすべての人に等しくチャンスがあるが、そのすべてがうまく運ぶとはいえないという現実の厳しさが身に沁みます。 もりむら やすまささんの「たいせつな わすれもの」を読みました。(ホームページトップ参照) ざんねんだけど、 いきていくことって たのしいことばかりじゃない。 たいせつな たからものが こわされたり、 ともだちが あなたを なかまはずれにしたり、 だれかの なにげない ひとことが あなたの こころを グサリと つきさす ナイフに なったり。
その いたみ、 そのいかり、 そのかなしもが、 きずあとに なって、 いつまでも うずいたり。 いきていくことは、 さかみちつづきの おおしごと。 しかたなく あと いっぽ、 だけど ほんきの あと いっぽ。 とちゅうで なげだしたら、 あなたの なかで さけぶ あのこえが ひとりぼっちで とりのこされる。 だから、 いっぽずつ。 いっぽずつ。 「進化認知学」という耳慣れない学問の研究者であるフランス・ドゥ・ヴァールの著した「動物の賢さがわかるほど人間は賢いのか」という本を「読み飛ばしました」。動物にはそれぞれの種の進化の過程で必要に迫られて備わった認知能力という知能が備わっているのに、人間がじぶん本位の価値観から動物の知性を歪めて評価して、動物は人間よりも知性が劣っていると結論づけるのは大間違いだ、というようなことが綿密な実証研究をあげながら書かれていました(ざっくりと言ってしまえば。とても乱暴な言い方ですが)。 ラットがじぶんの決断を悔やんだり。カラスが意地悪をした人の顔を長く覚えていたり。タコが人間の顔を見分けたり。チンパンジーが見つけた食べ物を気がつかなかったふりをして、後でこっそり取りに帰ったり。動物には人間に劣らないような知性が備わっているようです。それを見落としてきたのは、人間か勝手な解釈や価値観で動物にとってとても不自然でいびつな実験をした結果から、動物の能力を判断していたからだというのです。人間とは違う動物の視点から見える世界を「ウンヴェルト(環世界)」(周囲の世界という意味のドイツ語)というのだそうです。勿論、本書の表題の回答は「否」が正解です。人知を越えたより完成度の高い別次元の世界(ウンヴェルト)が存在するのは、なにも人間以外の動物の世界には限りません。人間の生を卒業した先に、人知の及ばない想像を越えたウンヴェルトが存在するかもしれいないということを誰が否定できるでしょうか? 三輪晴美さんを軸とした 毎日新聞生活報道部の 『乳がんと生きる ステージ4記者の「現場」』を読みました。実際に三輪晴美記者はステージ4乳がんなのです。ステージIV乳がんの患者さんをはじめ、乳がんに悩む全ての患者さんに「迷わず、あきらめない」を贈る励ましに満ちた作品でした。これも、やはり本というものの成すことのできる可能性を広げる貴重な著作であることは間違いのないことです。現実はフィクションの小説よりも重いこともあるのだ、という好例です。 恩田 陸の「蜜蜂と遠雷」を読みました。どんな作品を手がけたかはよく知っていましたが、この作家の作品を読むのは初めてです。作品の文学性はともかく、これだけの音楽に関する知識を満載した作品を仕上げるには相当の研究をされたのだろうと感心しました。音楽の素晴らしさを感じながら読んで、何度も涙することができました。合唱を愛する一音楽愛好家としては、ステージに上がる覚悟や気持ちのもって行き方はとても参考になりました。 この作品が何を言いたいのかなどという難しいことは考えずとも、臨場感あふれるピアノコンクールの世界に浸ることができました。それはそれで、本という媒体の成しえるとても素敵な役割だと思いましたので、小難しくこの作品の何たるかをうんぬんするのは野暮というものだと思います。努力賞に一票!! ポール・オースターはわたくしが繰り返し愛読する外国人作家の最右翼です。「冬の日誌」を読みました。読み慣れた柴田元幸先生の訳も心地よく楽しく読みました。老年期に入ったとオースターが思っている今、じぶんの肉体と感覚をめぐる回想録だそうです。性の芽生え、暮らしてきた家々の来歴、パートナーの遍歴、親との死別。興味深く、かけがえのない一文にも巡り合えましたが、オースターの最大の武器である執拗さは逆に辟易する欠点でもあるとわたくしは思っています(おそらくオースターが肉体的に限りなくスポーツマンとしての体力をもった人だということだと思います)。この著作でも何度もそう感じました。楽曲でも著作でも、これから展開されるであろう作品の進展がある予測される道筋を予感させたり、予測可能であるとき、わたくしは深い失望を禁じえません。例えば、「一年」という作品があったとき、一月の次には二月が来るだろうし、それが延々と12回繰り返されると思っただけで、わたくしは意気消沈してしまうのです。それは個人的な嗜好の問題ですからなんの批判にも説得にもなりません。単なる好みの問題です。そのうんざりする 執拗さを割り引いても、この著作の中に「人間にとっておそらく、終わりに至って愛すべき人間であることこそ最高の達成だろう」という一文を見つけられたことは大きな喜びであったのです。 じぶんにあった本に出合うと、その本をあまり速く読みたくないという衝動に駆られることがあります。あまりに面白いので敢えてゆっくり、じっくり味わって読みたいと思うのです。 残念ながらアメリカで評価の高い新人作家であるノヴァイオレット・ブラワヨという女性作家の手になる「あたらしい名前」はわたくしには面白くない退屈な読書で、読み進めることに苦労するものでした。わたくしの感想がこの作品の価値を下げることはけしてありません。わたくしにこの本の本当の価値を理解する感性と能力と興味がなかっただけのことです。アフリカのさまざまな国がどのような過酷な困難を乗り越えて独立なりを勝ち取れるのか、そのような国の人々にとって自由の国アメリカに違法滞在することがどのようなことなのか、本当は政治的にも深みのある著作に違いないのですが、どうしてもわたくしには猫に小判でしかなかった残念な読書に終わってしまいました。ごめんなさい、ノヴァさん! 大宅壮一ノンフィクション賞受賞者 のノンフィクション作家、奥野修司の「魂でもいいから、そばにいて 3・11後の霊体験を聞く」を読んだ。東日本大震災、津波で大切な人を突然失った方がたの霊体験を聞いた著作である。この霊体験を取材したものがノンフィクションとして成り立つのかどうかと悩みながら引き受けた仕事らしい。なにしろ、語ってもらったことが事実かどうか立証のしようがないし、再現性もなければ、客観的な証拠もないのだから、と。しかし、霊体験の取材を続けていくうちに、東北には「遠野物語」に出てくるような死者と共に生きるということをすっと受け入れる素地があることに気づいていく。物理学者の中谷宇吉郎は「大自然という大海のなかに網を投げて、引っ掛かってきたものが科学的成果で、 大半の水は網目からこぼれ落ちるんだ」と言ったらしい。デカルト以来わずか400年の近代科学の歴史で理解できないものを排除するのはおこがましいだろうと奥野はいう。サン=テグジュペリは「この世には見えるものだけでなく、見えなくても大切なものがある」と言ったとか。奥野は、ついにこう言う。「この世に存在するのはモノだけではない。ある人を慈しめば、慈しむその人の想いも存在するはずだ。この世界を成り立たせているのは、実はモノよりも、慈しみ、悲しみ、愛、情熱、哀れみ、憂い、恐れ、怒りといった目に見えない心の動きかも知れない。だからこそ人の強い想いが魂魄(こんぱく)となって、あるいは音となって、あるいは光となってこの世にあらわれる―」と。どこかで聞いたことのある洞察である。そう、アンソニー・ドーアが「すべての見えない光」で言いたかったこと、そのものではないか‼ ダニエル・アラルコンの「夜、僕らは輪になって歩く」をようやっと読み終えました。本当に長くかかった読書でした。作品を読むリズムは次第にできていくものですが、この作品はどこが大切な本流なのかという確信ができるまでに、本当に苦労しました。作者はペルー系の期待の俊英だそうですが、わたくしには暗くて希望のないストーリー展開が陰鬱で苦痛でした。それでも読み続けたのは主人公の若い俳優が大変な目にあうぞという思わせぶりなことばの断片の終着点はせめて知りたいという不毛な興味だけでした。恐らく殺されるのだろう、と思いながら……。しかし、結果は冤罪。心惹かれたのは、主人公の青年が収監され三年がたった時に、彼が見違えるように逞しい肉体と醒めたようなタフな精神力をもつ人間に変貌していたという一点でした。絶望のどん底で、人は生き延び、力強く逞しくなれるのかも知れないという希望を見い出せたからです。 ニック・レーンの「生命、エネルギー、進化」を、読んだ、と言えるでしょうか? 地球上でどのように生命が誕生し、真核細胞がどのようにして生まれたのかはよく分かりましたが、それが太陽系の宇宙でいかに稀少な出来事であったか、どのようにして生命に死が生まれたのか、実はあまりよく理解できませんでした。昔、学生の頃習った生化学の知識を呼び起こしながら読み進めましたが、肝心のエネルギー論の詳細なメカニズムは解読不可能でした。余りに専門的過ぎて、化学や物理学の知識が足りませんでした。その割には時間を割き過ぎた読書ではありました。それはニック・レーンの巧みな比喩に惹かれるあまりのことでした。生物と無生物の境界も、生きていることと死んでいることの境界も、突き詰めていくと判然としなくなるというくだりの説明はこころ惹かれるものでした。人類の知識の未熟さもとても説得力があり、納得のいくものでした。 第二次世界大戦のさなか、利発なドイツ兵の少年とフランスのパリに暮らしていた盲目の少女は運命の糸に手繰り寄せられるようにして フランス北岸の街、サン・マロで運命的な出会いをする。敵国どうしの、だが、少年は恋に落ちる。そうして、たった一日二人はことばを交わすが、少年は命を懸けて少女が街の外に出るのを助ける。少女は生き延び、少年は自死に近いかたちで間もなく命を失ってしまう。アンソニー・ドーアが2014年に発表した「すべての見えない光」は、反響を呼び、「ニューヨークタイムズ」のベストセラーリストに二年以上にわたってランクインし(2016年7月現在)、2015年にはピューリツァー賞を受賞し、バラク・オバマ大統領の読書リストにも入るなど、あらゆる方面からの注目と称賛を浴びているという。わたくしもこの本との出会いに運命的なものを感じています。年老いた盲目の少女の「魂の巨大な定期便は煙突の上を流れ、歩道に乗り、人々のジャケットも、シャツも、胸骨も、肺も通り抜けて反対側に出る―空気は生きたすべての生命、発せられたすべての文章の書庫にして記録であり、送信されたすべてのことばが、その内側でこだましつづけている」という考察が胸に迫ります。 ペーター・シュタイムは徐々に存在感を増してきたスイスの作家です。わたくしより四歳若い。「誰もいないホテルで」を読みました。短編集というのは、あまり好きではありません。アリス・マンローでさえ、読み始めようとすると、やれやれというような気分になるのですから。やっと、作品になれ始めたころに終わってしまうので、何冊も本を読み始めなくてはならないような、体力の消耗を感じるのです。面白い本でした。愛蔵本にできなくもないくらいに。わたくしが珍しく読む日本人作家二人が関わっている本でした。まず、堀江敏幸が帯の紹介をするほどに押している本です。松永美穂訳の短編10のうちの、「スウィート・ドリームズ」という作品は、英訳が「ニューヨーカー」にも掲載されて、それを村上春樹が「甘い夢を」というタイトルで日本語に重訳して「恋しくて」という本に収めているそうです。村上の「恋しくて」は読んだ記憶がありますが、「甘い夢を」を再読して比較してみようなどという殊勝な研究熱心さはありません。わたくしは、生真面目で農作業にしか興味のなかった青年に恋心が芽生えていく過程を扱った「眠り聖人の祝日」という作品が好きでした。ちなみに、「眠り聖人の日」というのは、ローマ時代に洞窟に閉じ込められ、二百年間を眠りながら生き延びた七人のキリスト教徒が発見された日のことだと 、小説のなかで触れてありますが、キリスト教に本当にそのような日があるのかどうかは調べてみましょうか!? アトゥール・ガワンデ「死すべき定め」は、近年の読書の成果、5本の指に入る名著でした。忘れられない一冊となりました。アメリカの現役の外科医の筆になる本書は米国でも大きな反響があったそうです。医学は患者をより長く生かすために すべての心血を注ぎ、豊かに、より良く死ぬための配慮には決定的に欠けているというのです。細分化され、ルーチン化された医学的治療は、老化と病気による人の死において人生の最期を迎えたときに満ち足りて生きるという視点が欠落しています。「医療関係者は役に立たない、なぜなら、治せる患者でなければ、医師は患者に興味を示さないからだ」、と著者ははっきり言い切ります。終末期にしっかりと時間を割いて医者と患者が話し合うことで、患者は魂を救われ、一人の人として扱ってもらうことで、患者はどんな治療になら何が大切だから耐えられる、応じられるけど、これこれはやめてほしいという判断ができるのです。病院のICUで何も話せない状況で、これでもかという乱暴な医療行為を勝手にされて、何もじぶんの大切なことを伝えられずに逝ってしまうことは本当に辛い、無意味な死に方だと知りました。著者は言います。「医療従事者としての責任は、人を人として扱うことだ。人は一度しか死ねない。難しい話し合いに前向きに取り組む医療従事者が必要だ。今まで見てきたことを伝え、来るべきものに対する備えを手伝ってくれる専門家にならなくてはならない」と。緩和ケアという医療分野は、そのようなことを大切にして取り組む、よりよく逝くためのかけがえのない医療だと思います。 ジュリー・オオツカの「屋根裏の仏さま」を読みました。個人的な理由でとても長い時間かかってやっと読み終えました。本を読むということは、精神的な余裕のあるときでないと困難な作業であることが、よくわかりました。この本は20世紀初頭にいわゆる「写真花嫁」として米国になかば詐欺のように騙されて渡った日本人女性たちが、王子様のような男性をまっかな嘘に よって想像していたのを裏切られ、まったく貧相で貧乏な小作農の夫との結婚生活と過酷な労働の果てに、太平洋戦争が始まり、築き上げたすべてを失って、強制収容所に入れられるまでを描いています。無数のわたくしたちという一人称で、苦労と徒労と諦めのことばがこれでもかと繰り返され、ストーリーの展開があるわけでもなく、現実を叩き付けられるようで、読むのが忍耐力勝負みたいな本でした。これはこれで、忘れてはならない悲惨な歴史的真実を克明に綴っているのだけれど、やっぱり読書を楽しむということからは遠いところにある本ではありました。「つまらないなら、止めればいいのに」と家内はよく言いますが、読み始めたら、読み飛ばしてでも読み終えたいと常々考えているのです。困ったものです。 グードルン・パウゼヴァングの「片手の郵便配達人」は、第二次世界大戦でドイツが敗北して、ヒトラーや戦争に人生を翻弄されるドイツの山間部の片田舎で暮らす市井 の人々の生活を淡々と描いた佳作でした。戦争で片手を失った青年郵便配達夫ヨハンの目を通して、戦争によって人生をめちゃくちゃにされる人々を、戦争の場面も描かず、大きな事件も無く、しかしだんだんと歪(いびつ)になっていく様だけを静かに描いています。そうして、最後にヨハンの人生は、せっかく戦争も敗戦というかたちで終わり、恋すらを覚え、未来に希望を持とうとした矢先に、皮肉な運命の悪戯によってあっけなく突然断ち切られてしまうのです。すべての死は偶然の悪戯で突如として、誰の目の前にも現れうることを、わたくしのような年齢になれば頭では、知識としては分かっていても、それが、戦争や病魔によって暴力的に現実問題としてわが身に降りかかってくると、知識で理解しているような痛みどころではないことを人はやっと本当に知ることになるのでしょう。戦争のおぞましさは突出した異常な状況ですが、誰の人生にも、平和な生活の中ででさえ、死は無情にも冷笑しながら訪れることです。それは、けして静かに、ではなく、激震を伴いながらやってくるのです。他人には、さもなにごとでもないようにしか見えなくても……。 |