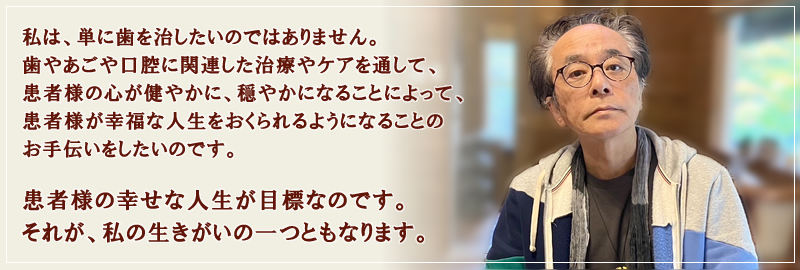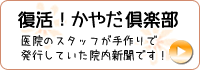読書のお話 その4
|
「阪神大震災遺児たちの一年 黒い虹」(あしなが育英会編、福田義也監修)を読みました。みんなが異口同音に言っていることはよく分かります。一番大切なものを失ったり、大震災にあって突然大切な人を失ったりした人たちは、みんな同じことを感じて、同じことを言っている。その中でとても気になった男性のことば。妻と保育園の娘を亡くしました。まだ赤ん坊の息子と(男性)の二人っきりになってしまいました。生前、妻は自分の命にかえてでも子どもを守ると言っていたように、息子はほとんどケガもなく助け出されたんです。悪い人が先に死ぬって言いますが、あれはウソですよ。娘なんてまだ幼児です。死んだこと、本人もまだ気づいてないんじゃないかなあ。なんで、神様は二人を連れて行ったんでしょうね。今、息子を実家の両親に預け、私は一人暮らしです。私の部屋に二人の遺骨を置いているんですが、一人、部屋に帰ってくると、これからどうしたらええんやろう、と言ったままシーンとしてしまいます。小さい息子を残して(天国に)行こうなんて思っていないと思います。ずっと近くにいたいと思ってると思うんです。今回の震災で「復興」という言葉がよく使われていますが、その言葉は嫌いです。私たちみたいな者にとっては、壊れたものは壊れたものとしてそのまま残るんです。心の傷は残ったままなんです。やり直すのではなく、また新しいものを作っていこうとしなければいけないんだと思います。 マルクス・ガブリエルの「新実存主義」を読むのを諦めました。同書の共著者である老哲学者が、ガブリエルの新実存主義という言葉の使い方をきちんと理解できたかどうかは自信がない、と言っているのです。専門家が理解できたかなあというのですから、私が十分理解できなくても仕方ありません。ただ、なんとなく理解したのは、宇宙という最大に巨大な存在よりも、「世界」や「こころ」というものはもっと大きな包括を示すものだということです。宇宙も明らかな存在だけれども、「世界」や「こころ」は存在としては説明できない、広がりをもったものだということです。違った存在なのです。ガブリエルは専門用語を使い過ぎているように思います。専門用語の定義をきっちり腹に入れていないと分かりにくい議論の展開に私の頭では追い付いていけなかったのです。おそらく、文章の中にきちんと定義を示しているのでしょうが、私の頭はその定義を述べている個所をうまく拾い上げることができなかったのです。(´・ω・`) 普通なら、だれだれの「なんとか」という本を読みましたと書くところですが、マルクス・ガブリエルの「なぜ世界は存在しないのか」を読もうと試みたのですが、読めませんでした。もう一冊の彼の著作「新実在主義」は読もうと悪戦苦闘しています。私たちが一般的に考える「世界が存在していないのだ」ということを書いているのとは違うということは確かです。これは、厳密な言葉の定義と、歴史的に積み重ねられてきた哲学的知識と思考を検証しながら、「世界というものは存在しえない」と言っているのです。これを、私が「世界」と考えているものは存在しないと思った方がいいということなのかどうかは、読めなかったのですから分かりません。ただ、我々が漠然と「世界」という言葉を使うことは、気をつけた方がよさそうには思われました。例えば、「世界平和のために」と漫然と使ってはいけないような感じはします。そうだとするとこの本は私にも意味があると思います。「世界が穏やかでありますように」と言うのは、ちょっと待って!と。 我々が漠然と認識している「世界」という言葉の意味をしっかいり考えてから、使った方がいいよ!なら、分かりますので。その真偽は分かりませんが、良い警鐘を鳴らしてくれます。「新実存主義」を早く片付けて(つまり、やっぱり分からなかったと言うんだったら、さっさと言ってしまって)次に読みたい本を読みたいと思っているうちに、読み始めたいのです。ガブリエルのようにちょっと訳の分からないことを書き始めました。折しも、ごく最近NHKテレビの特集番組で彼を追いかけて様々な議論をしているものが放映されました。それをビデオに撮ったものを見ようとしているのですが、マシンガンのようにアグレッシブに論を展開する彼の言葉を聞いていると、読書と同様に食傷気味になって、ビデオを途中で止めてしまっています。ガブリエルさん、ごめんなさい。凡人には、あなたの頭の回転速度には着いていけないところがあります。 ある晩、父が失踪する。若者は大学進学のための金を稼ごうと、イスタンブール郊外で井戸掘り職人の助手を務める。そこで印象的な赤い髪の自分よりはるかに年上の女芸人に恋をし、二人はある晩結ばれる。その因果はまわりまわって、主人公と思われた若者は物語の大詰めで、一人の登場人物に過ぎなかったことが分かる。トルコで初めてノーベル文学賞を受賞した、私の愛読するオルハン・パムクの最新作「赤い髪の女」。主人公と目された男の青年期から壮年期までの心象と実人生を瑞々しく描きながら、その男はある日突然首をへし折られてわき役へととって代わる。そこに、深い悲しみと絶望を感じずにはおられません。パムクは人生なんて所詮そんなもんだと言いたいのかも知れません。1980年代から現在に至る「イスタンブール叙事詩」の最新作らしい。作品のいわんとすることの内奥のことは兎も角、私には再びトルコにおけるインテリ、ブルジョア層の脆弱さを連綿と綴った作品に思われて仕方がない。それは、日本人としてこの作品を読む私自身に突き付けられた弱さとも思われて、共感を覚えるのだ。この作家の「雪」を読んだ時に覚えた感慨と等しい。インテリ、ブルジョア層のひ弱さは私にも当てはまる劣等感だからである。 「生き物の死にざま」(稲垣栄洋作)という本を読みました。端的に言えば、生物は子孫を残すためだけに様々な戦略を駆使している、という内容の本ですが、その作戦があまりにも悲しい。有名なサケは1万6000kmにも及ぶ旅をして、ふるさとの川を遡上するのですが、繁殖行動を終えるとサケは死ぬようにプログラムされているのだそうです。最初の繁殖行動をおこなったオスのサケも死へのカウントダウンが始まるが、命が尽きるまでメスを探し続けて、繁殖行動を繰り返すのだそうです。卵を産み終えたメスも、しばらくの間、卵に覆いかぶさって守りながら命尽きていくのだそうです。春になると、産み落とされた卵たちはかえり、小さな稚魚たちが次々に現れる。その稚魚たちに豊富なプランクトンを提供するのは、力尽きて死んでいった親たちの死骸が多くの生物の餌となり、その生物の営みによって分解された有機物が餌となって、プランクトンが大量に発生して、稚魚たちの餌となる。カゲロウの成虫の寿命は数時間しかなくて、その時間のうちに交尾を繰り返して命尽きていく。数時間の命しかないカゲロウの成虫は食べるための口が退化して無いのだそうです。数時間の間子孫を残すために交尾だけをするカゲロウの成虫にとって食べる必要はないからです。 1951年生まれのイギリスの作家で、本作で二度目のカーネギー賞受賞という快挙を成し遂げた、ジェラルディン・マコックランの「世界のはての少年」を読みました。スコットランドの西岸沖に浮かぶ西の果ての島々と離れ岩には「世界が終わっても、音楽と愛だけは生き残る」という言い伝えがあるそうです。その孤島の男と少年たちが生計を立てるために船に乗って離れ岩に行き、そこで海鳥の肉や羽根や油を収穫する、その岩礁に迎えが来ず取り残された男たちの生き残りをかけた物語です。主人公のクイリアムが大変な苦難を乗り越えて生き残り、最愛の女性と心の中で念じ続けたマーディナ・ギャロウェイと奇跡的な再開を果たして、「きみはぼくの吸う息。きみはぼくのこころを羽ばたかせて、空高く舞い上がらせ、その手で落ちないように支えてくれる。君のためにぼくは生まれ、きみのためにぼくはこれからも生きていく。死が僕を連れ去るか、あるいは世界がおわるまで」という言葉を吐くためにだけの苦難の物語ではないかと、この言葉をより真実の籠ったものにするためにだけ仕掛けられた史実を膨らませた冒険譚なのではないかと、私は思いました。 梨木香歩 の「やがて満ちてくる光の」というエッセイ集を読みました。この人が自分と同じ年齢であることを初めて知りました。「西の魔女が死んだ」くらいしか読んだことがなかったのですが、この本を読んで梨木さんという人がとても謙虚で真摯で、しかも好奇心旺盛な「ふつうの神経」の持ち主であることがよくわかりました。しかし、偶然や奇遇を信じる、現実的な凡人を突き抜けたところのある人だということもよくわかりました。情熱的なロマンチストな面もおありだということです。もっとほかの本も読んでみたくなって取り寄せました。作家と作品は別物という文学者も多いですが、梨木さんはご自分の論理や直感の到達点をそのまま、その時点で、作品にされている信頼できる作家だと思いました。3.11に関して 「あるとき、どこの局だったか町の路上に立ったテレビのアナウンサーが、たぶん彼も動転していたのでしょう、目を吊り上げて、『非常時なのですから』と叫ぶように言ったとき、とても不吉な予感がしました。非常時、という言葉を合図に、あっというまに心ひとつにまとまる民族、他国のメディアも賞賛するという、・・・・・・あの戦争中の空気―異質であることを許さない・・・・・・自分を犠牲にすることを強いられる―そういう空気・・・・・・再び醸成される気配を、その言葉に強く危惧したのです。緊張し過ぎてはならない。大変なときではあるけれど、緊張し過ぎてはならない。「勢い」を、「真摯に人を思う」、そこで止めておかなければならない。個人を、群れに溶解させてはならない」信頼に足る良識をもった作家であり、人間であると思いました。 レティシア・コロンバニの「三つ編み」を読みました。フランスで85万部を突破し、世界32言語での翻訳の決定した評価の高い作品です。インドの寒村で暮らすカーストの下層民、不可触民の女性、一日中、一生、他人の糞便を素手で拾い集める仕事をする運命にある女性と、シチリアのパレルモで他人の髪の毛をカツラ用に仕立てる職人の家の娘として生まれてきた女性と、カナダのモントリオールでエリート弁護士としてのし上がってきた女性。三人が三様に過酷な運命に翻弄され、もがき苦しみ、その果てに、やがて三人の人生が 重なり合うことになります。女性だからこそ書ける女性の強さを、簡潔な文章で書ききった秀作でした。やはり、女性はおそるべしなのだ! レベッカ・ソルニットの「迷うことについて」を読みました。訳者あとがきで述べられているのですが、原題の中で使われている〝Getting Lost”は「人間が失われるものとなること」、「人が迷い、紛れ、失われ、消え、見えなくなること」だと書かれています。「人間だけではなく、物や動物が失われることにも触れられている」、と 。最初からなにか違和感のような、しっくりこない思いで読んでいたのですが、途中で著者が女性であることが分かって、合点がいったのです。私には外国人の名前が女性なのか男性なのかという知識すらなかったのですから。著者は「物事は本性からして失われるものであり、それ以外の帰結はない」と述べています。とても繊細で、なにか研ぎ澄まされた直感的な表現が女性らしく感じました。省察のなかでとても象徴的なもの、隔たりの青〝The Blue of Distance”。「世界はその際(きわ)や深みで青を帯びる。この青は迷子になった光の色だ。スペクトルの青側の端に位置する光は、大気や水の分子によって散乱するために太陽からわたしたちのところまでまっすぐには届かない。水にはもともと色がなく、浅い水は底の色をそのまま透き通らせる。しかし深みは散乱した光線に満たされ、水が澄んでいれば澄んでいるほど濃い青色になる。空が青いのも同じ理由だ。けれど地平線の青、空に溶けてゆくような地表の色はもっと深い色をしている。現実でないような、憂いをたたえた、はるかな見通しのいちばん先に見える青。隔たりの青。わたしたちまで届くことなく、その旅路をまっとうできなかった迷ってしまった光。この世に美を添えるのはその光だ。世界は青の色に包まれている。 もう長い間、視界の限界にみえる青に心を振り動かされていた」 私的な色彩が濃い作品であると訳者がいうこの省察は、しかし、あまりにも美しい悲しみに満ちている。 ミヤギフトシの「ディスタント」は何で紹介されて読み始めたのだろうか? 前半三分の二を四苦八苦しながら、まあ、青春小説かなと思いながら、ところどころにホモセクシャルな雰囲気を感じながら読んではみたのですが、最終章のストレンジャーは飛ばし読みもいいところ。やはりホモセクシャリティーが現在的でファッショナブルな雰囲気なのかなあとそれくらいしか読み取れずに、読み切れなかった著作でした。本当は沖縄の置かれた位置からもがきながら這い出そうとする若者を描いているのかも知れませんが、私は読み通してもいないのですから、なにもコメントはできません。若い人たちがこれを読んだらどのように感じるのだろうか? とちょっと気にはなるところですが……! |