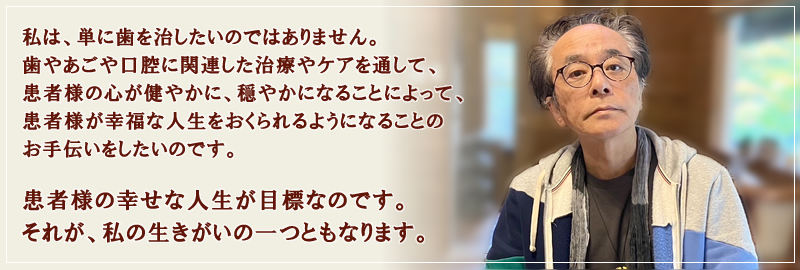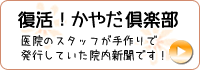読書のお話 その7
|
イーユン・リーの「水曜生まれの子」を読んだ。マザーグースで水曜生まれは悲しみに暮れ、木曜生まれは旅に出る、そうな。彼女は1972年に研究者の父親と教師の母親のもとに北京で生まれた。北京大学で生物学を学び、渡米してアイオワ大学で免疫学の修士号を取得し、博士課程に進んだ。結婚ののちに作家に転身した。この本には子供を亡くした母親がよく登場した。当たり前だ、彼女は鬱病で自殺未遂、そして、その後にわが子が自死した。彼女が言う。「不幸と悲しみは違います。不幸と喜びは両立しません。不幸はつらい状態に似て、よくない事です。そして、私は不幸ではありません。悲しいのです。とても悲しいと言えます。悲しい過去があるのです。でも不幸ではありません。なぜなら悲しみと喜びは両立しうるからです」「パレスチナやイスラエルで人が亡くなっているのにー花を植えて何の意味があるのか。本当に悲しいとき、意志力をもって、ケーキを焼いたり庭仕事をしたりすることに、喜びを見出せるのです」 ジュヨン・チーヴァーの「チーヴァー短編集」を読んだ。素敵な作家に巡り会えた。チーヴァーは1982年にがんのために70歳で亡くなったそうだ。短編の名手で、短編のファンの多い本国アメリカでは死後ますます評価を高めているらしいが、Writer’s writer (作家が愛する作家)として玄人受けする作家らしい。レイモンド・カーヴァーからチャールズ・バクスターまで、現代アメリカで短編の名手といわれている作家はほとんどが彼の影響を受けているそうだ。確か村上春樹はレイモンド・カーヴァーファンだったと記憶しているから、彼もファンの一人に違いない。ジョン・アプダイクはチーヴァーの短編を評して「天使の羽根のペンで書かれた作品」と言ったらしい。「空は青かった。音楽のようだった。私は芝生を刈り終えたところだ。芝の匂いがあたりに満ちている。その匂いをかいでいると若い頃よく感じた恋の予感、きっと恋が始まるに違いないという気持ちを思い出した」「人生のなかで昂揚したした気持ちを生んだり絶望を生んだりするするのは、一貫した事実のつらなりというより、説明不可能な偶然の衝突なのだ。私が望んだことは、このとりとめのない世界で私の夢に正統性をあたえることだった。夢のほうが、現実よりも確かなものではないかと考えたかった」「私は次第に取り残されてゆく。人生の晩年を迎えてゆく。これまで見ていたものがわからなくなってくる。あの光はそうしたことをやさしく暗示しているように思えた。静かに老年を迎えるのだと思うと心地よかった」 あの「存在の耐えられない軽さ」のミラン・クランデラが昨年逝去した。だから、という訳でもない、訳でもないけれど、「緩やかさ」を読んだ。文学的なエロティシズムとポルノグラフィティーとの違いがどこにあるのか僕には分からないけれど、とにかくエロティックな作品だった。それが一番表現したいことではないにしても、 エロティシズムが重要な作品の要素であることは間違いないことだと思う。作品のごく一部分に密かに仕込まれた、「ひとりの人間が自分の思っていることを公言しただけで、みずからの人生の意味を剝奪されることもあった国からやってきた」一人の科学者が学会で自由な発表をしようとする寸前に、感動に抗しきれなくなって、学会発表の原稿のことを忘れて予期せずじぶんの感動について語り始めてしまうくだりは、良質な文学の片鱗だと思う。 クレア・キーガンの「ほんのささやかなこと」を読んだ。前回読んだ本の原題は「Minor Detail」今回のは「Small Things Like These」意味は違うけど本当に似たような題名だ。男は迷いながらも一生後悔するようなことは嫌だと、勇気を振り絞って権力にあらがうことを決める、それが、どんなにささやかなことだとしても。クレア・キーガンはデビュー作からずっと発表する作品ごとに賞を獲得しているアイルランドの気鋭の才女だ。本作もニューヨーク・タイムズ紙による「21世紀の100冊」に選ばれ、ブッカー賞、ラズボーンズ・フォリア賞の最終候補に選ばれた。オーウェル政治小説賞、ケリー賞のアイルランド文学部門を受賞。2023年にはアイリッシュ・ブック・アワードからオーサー・オブ・ザ・イヤーに選ばれている。アイルランドという国で起こった悲惨な歴史を知っているかいないかによって、作品の価値は大きく変わるだろう。残念ながら僕は後者だ。だから「ほんのささやかなこと」を蛮勇をふるって断行した男の本当の価値を正確には理解できていない。 読書も大変だ! それなりの知識が要求される。やれやれ、、、、、、 1974年生まれのアダニーヤ・シブリーの「とるに足りない細部」を読んだ。読み始めてすぐ後悔した。作者はパレスチナの生まれ。本書は2020年の全米図書賞翻訳部門の最終候補となった。2021年には国際ブッカー賞最終候補。2023年には独リベラトゥール賞を受賞したが、イスラエルによるガザへの攻撃が激化するなかで、授賞式は中止となった。同賞の主催団体が「イスラエル側に完全に連帯する」との声明を出したのだ。この決定に対して作家や出版関係者などを中心に世界中から抗議の声が上がっている。また、アラブとイスラエルの対立を扱った本を読み始めてしまった、と思った。僕にはなんの力もない 。判断材料も、意見もない。現実に半世紀前(1949年)に起きたイスラエル軍部隊によるベドウィンの少女レイプ殺人事件と2004年ころにその事件を衝動的に追いかけるパレスチナ人女性の悲劇的な結末が二部で書かれている。シブリーはじぶんの作品が安易に政治や現実と結び付けられることなく、あくまでもフィクションとして読まれることを望んでいるらしいが。そのような作者の意図を打ち砕いて、ガザで進行している事態と本作は確かに響き合わざるを得ない状況にある。無理矢理にこの文学作品はガザの現実によって捻じ曲げられ「血を流しているのだ」! 僕の読書も、頭の中でまた、あのパレスチナ問題の読書だ!と無味乾燥な範疇に分類されてしまう。痛ましいことだ! 関西学院大学 悲嘆と死別の研究センター に所属されるお二人坂口幸弘センター長と赤田ちづる同センター客員研究員が執筆された「もう会えない人を思う夜に」を読んだ。私が読後の感想をつらつら書いたところで、何の意味もありません。思い当たる方は是非読んでみられるといいと思います。何かのきっかけを掴めるかも知れません。 ヨン・フォッセの「朝と夕」を読んだ。「言葉で表せないものに声を与えた」と評された2023年のノーベル文学賞受賞作家です。「言葉にすることはできない、それは言葉より 哀しみに近いものだから」フォッセの著作は、小説、戯曲、詩、エッセイ、翻訳など多岐にわたりますが、繰り返しの多用と句点がないのが特徴で、小説全体を一つの長く切れ目のないテキストと捉え、終止符を打ちません。フォッセには自分が書いているという意識が薄く、物語はすでに出来上がっていて、自分はただ耳を澄ませて物語を聴き取り、消えてしまう前に急いで書きつけているだけだと言うのだそうです。「書くことは自己表現ではなく、むしろ自己離脱だ」と語る言葉はフォッセの態度をよく表していると訳者が書いています。フォッセは私と同い年のノルウェー人作家です。「朝と夕」もすでに死んでいるか死に行こうとしている男の見るもの聞くものを、時間や時空や記憶や現実を歪めたり、逆転させたり、行きつ戻りつしながら物語が進行しているように思いました。不思議な作品ですが、不愉快ではなく、恐ろしくもありませんでした。むしろ人間は死というものをこのような時の流れの中で迎えるのかも知れないという、安堵に似た気持ちを覚えました。そうして、次に自分を追って同じような死を繰り返す子孫たちは 、しっかりとその先達の死を受け入れているように見えました。 恩田 陸の「スプリング」を読んだ。久しぶりの日本人作家の物語文学。エロティックでもあり、クラッシックバレーの才能を持つ天才たちの輝きや孤独や格闘に羨望の気持ちを抱きながら読んだ。久しぶりの快調な読書だった。とりたてて何かを意図して訴えるような文学ではなかった。その臨場感とノンフィクションを読むような説得力が命かな? 主人公HALのどこか遠くの世界を見て、目の前に広がる現実にはたいした興味を持たない眼差しには、惹かれるものがあった。そのように生きたいとまで思った。クラッシックバレーにはなんの興味もなかったが、一度本物のステージを見てみたくなるのは僕だけだろうか!? マリーケ・ルカス・ラインフェルトは1991年にオランダで生まれ育った若者です。「不快な夕闇」は彼が2020年のブッカー国際賞を史上最年少の29歳で受賞したデビュー長編小説だとか。兄の事故死のあとに残された家族の様子を、徐々に暗く沈鬱になっていく様を描いた、少し癖のある小説でした。題名通りにとても愉快とは言えない読み進めるのが重苦しい作品で、とりたてて何かが起こる作品ではなかったので、主人公のような十代前半の若い兄弟や友人たちの奇妙な性癖が歪な感じを醸し出している作品でした。帯にある通り「日常の中にある驚くべきものを見出す力と詩的な視点によって、新たな世界が描き出される」作品でした。日本には意外と多いタイプの作品ではないかと勝手に思ったり致します。もう少しストーリーの展開のある明るくわかり易い作品を次こそは選択したいと思いながら遅々として読み進めた作品ではありました。 イアン・ボストリッジの「ソング&セルフ」を読みました。イギリスを代表するテナーで大英帝国から勲章までもらっている超有名歌手のようですが、私は存じ上げておりません。オックスフォード大学で近代史の博士号を持つ知識人だそうです。ジェンダー、人種、死をめぐる作品や音楽家の省察。ジェンダーを論ずるなかでモンテベルディーが登場したり、ずっと語り継がれるのはブリテン。チャイコフスキーやブリテンのジェンダーにかかわる性癖は全く知らないけれど、音楽家は優雅で気持ちの良い活動をするから長生きな気はしていますが、我がままで意地っ張りで、自分本位、意地悪な性格の人が多いのかも知れません。穏やかで人徳があって、達観しているようなごじんなら、敢えて音楽などして自分を歪に表現する必要はないでしょう。イライラしてどうしようもなく自分本位で、自己顕示欲が強いから音楽などなさって、自己表現するのではないでしょうか? 最近、プロの音楽を専攻する方々を見ていてつくづくそう思うのです。私の見渡せる音楽家には狭い狭い限界はありますが、 けして現在のイスラエルのガザ地区への戦争を予測してではないのでしょうが、それぞれテロや射撃によって10歳と13歳の愛する娘を失ったイスラエル人とパレスチナ人の、深い悲しみに根差した友情と、争いをやめる以外に方法はないのだと訴える二人の男たちの過酷な現状が赤裸々に描かれている、コラム・マッキャンの「無限角形 1001の砂漠の断章」(2023、04,20日本版初版)を読みました。最近の私の読書のスピードの愚鈍さの例にもれぬ、長い時間を要した読書でした。偏見や誹謗中傷などに振り回されながらも、無益なイスラエルとパレスチナの戦争を、互いに愛娘を失ったという視点から悲しくも戦争の無益さを厳格に訴えた作品でした。著者のコラム・マッキャンは2009年に「世界を回せ」で全米図書賞を受賞したアイルランド出身の作家です。本作はイギリスのブッカー賞にノミネートされた佳作です。『憎んでいる時間はありません。痛みをどう使えばいいのか、それを学ぶ必要があります。血ではなく平和のために投資してください。私たちはそう言い続けています。パレスチナでは、無知とだけは知り合いになるな、と言われています。私たちはイスラエル人とは話しません。許可されていないんです。パレスチナ人もイスラエル人も、互いに話したいとは思っていません。だから相手がどんな人間なのか想像できない。そこに狂気が潜んでいます。どんなに沈黙が支配しているように見えても、私たちに声がないわけではありません。私たちはこの土地でどうすれば一緒に暮らせるか、それを学ぶ必要があります。死んでから墓の中で共存し合ってもしかたないでしょう。 私たちパレスチナ人は、多くの人にとって人間として存在していません。私たちは公的にはどこの国の人間でもないんです。一箇所だけ、あなた方の刑務所でなら私は存在するかもしれません。 殺し合いを続けなければならないなんて、どこにも書いてないでしょう? 彼らは私の娘といっしょに私の恐怖心まで殺しました。 私自身が占領されず、権利を持ち、移動が許され、投票が許され、人間であることが許されれば、何だって可能です。』 内田 樹の「村上春樹にご用心」を読んだ!? 村上春樹の最新作を読んで、その余韻に浸っていたくて、つぎの本に進められないでいたら、悪友が紹介してくれた。つまらない本だ。村上春樹が文壇からも、日本の評論家 からも評価されないで孤立しているということはわかったけど、じゃあどうしてと読み進めてもはっきりとは、つまり私のような頭の悪い者にもわかるようにちゃんとは説明してくれない。はっきり言うと差し障りがあるのだろう。つまりそういうことなのだろう。村上春樹の作品は洗練されていて、清潔感にあふれていて、若い男女の恋を語らせたらちょっとほかの日本の作家にはできないことをポンと提示してしまう。内田 樹が大いなる村上ファンであることはよく分かった。なんだこのおっさん、どんな出自? と作家紹介を見てみたら、ぼくより9歳上で、しかもかの東大仏文科の出身だった。それならもうちょっと真剣に読んだのにと思ったがもう遅い。その中に心に刻まれた文章はあった。「これはやはり霊的生活の比喩じゃないかなと思います。村上春樹ってそういう話ばかりしている人ですからね」「およそ文学の世界で歴史的名声を博したものの過半は死者から受ける影響を扱っている。文学史はあまり語りたがらないが、これはほんとうのことである。 近いところでは村上春樹の作品はほぼすべてが幽霊話である(村上春樹の場合は幽霊が出る場合と人間が消える場合と二種類あるけれど、これは機能的には同じことである)」夏目漱石だってそうだ。吾輩は猫であるの猫は執筆時点ではすでに死んでいる、あれはテクスト全体が死猫からのメッセージ。こゝろもそうだね。あれも第三部からは死者からのメッセージだ。死者は死んでもう存在しないから、私たちには何の関係もない、などとお気楽なことを言う人間は文学とも哲学ともついに無縁である」 長い長い時間を掛けて、村上春樹の「街とその不確かな壁」を読んだ。面白かった。村上作品の全体を通しての評論めいた解釈をするのはあまり意味がないし、作者自身もなんらの意図を持たずに書いているのではないかと思う。村上作品の面白くてしようがないとう側面は、その場面設定の妙にあると思う。書かれている場面設定がイカしているし、登場人物の会話がまたイカしている。はっきり言ってしまえば、jazzyなんだと思う。白けてしまってはjazzという音楽は成立しない。何を言いたいのかという意図が透けて見えてはjazzはつまらない。人々を唸らせる、洗練と意表を突いた展開。これが命かな? と、jazzをなんにも知らない私は思う。ただ、この50年近く断続的に合唱に浸ってきた私から言わせてもらっても、先が見えたり、意図が見え見えの音楽なんてつまらない。意表を突いた和音の進行、調整の展開があってこその音楽だ。村上春樹の卒業制作に近い一作なのかも知れないと思いながら、じっくりと味わいながら読ませてもらった。得も言われぬか佳作であることは疑いの余地がない。 坂本龍一がつい先ごろ亡くなった。70代前半じゃないかと思う。また、早すぎる死。坂本龍一と福岡伸一の対談「音楽と生命」を読んだ。福岡先生の著作は何冊か読んだことがあったから、先生の思考の方向はおおよその見当がついていた。坂本龍一の音楽をとりたてて聴いていたわけではない。むしろほとんど受動的に耳にしてきただけだ。しかし、この人がとても博識で音楽以外の事柄にも豊富な知識を持っていたことには驚かされた。二人の会話はいつもロゴスとピュシスの対立ということに話題が収斂していくのだそうな。簡便に言ってしまうと、ロゴスとは人間の考え方、言葉、論理といったもので、ピュシスとは人間も含めた自然そのものらしい。一本の木が若葉を茂らせる時から樹齢を重ね倒木となる時まで多くの生命を育み、大きな自然の連環を形作ると同じように、人間の死も次の世代にある種の贈与を残す利他的行為だと言う。個体の生命が有限であることが、すべての文化的、芸術的、あるいは学術的な活動のモチベーションになっているのだと。 おおいに賛同。 |