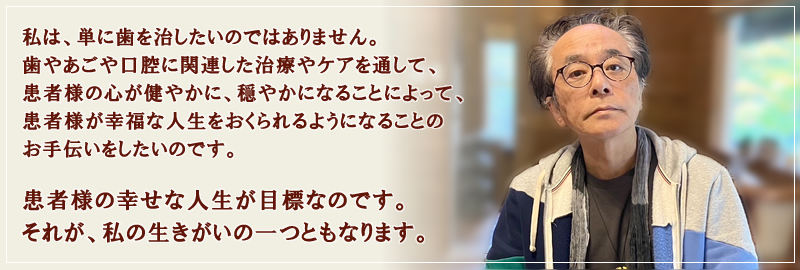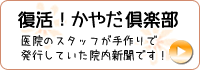読書のお話
|
私の知り合いの女性は村上春樹をあまりよく思っていないようなのです。彼女曰く、「村上春樹は女性蔑視だ!」とか。そのことの真偽は兎も角。村上春樹9年ぶりの短編小説集を読んでいて、そんな言い方をする人がいるかも知れないな、と思いながら読み始めたのは事実でした。この本の表紙が、この作品集の終わりから二つ目の短編の一場面を描いているのも、当然だと思いました。そう、その短編が一押しだったのです。村上春樹は私が定期的に読む数少ない邦人作家ですが、この人の真骨頂は、現実にはありえない世界を、説得力を持って、魅力的に描くところだと思っているからなのです。人間は、現実のせせこましい世界でばかり生きているのではなく、実は、妄想や幻想や、飛躍や空想によってこそ、人間の真に生き抜く力を与えられながら生きているのだ、というユダヤ人作家の作風を思い起こさずにはおられません。羊男が話したり、魚が空を飛んだり、隧道や井戸に捉えられたり、……、それこそが、村上春樹の世界なのです。人々が魅了される。でも、残念ながら、この作家は、再三メガヒットを飛ばす、ポップス歌手が押さえているツボみたいなものを、あまりに身に着けすぎていると思うのです。彼が、それを意識してるか、いないかは、また別の問題ですが。この作品集の最後の書き下ろしを、「女」に捨てられた男は淋しい、みたいな作品にしたのは、この作家の健全な素直さだと思います。わたしは、そこに、ほだされもします。それに、わたしが、「僕の永遠の一部である十四歳の僕が、優しい西風が僕の無垢な性器を撫でるたびに勃起する」ような少年のこころを失いたくないと真剣に思うのは、この作家の非凡さがわたしを魅了していることの証左かも知れません。 M.G.ヴァッサンジの初めての邦訳「ヴィクラム・ラルの狭間の世界」を読みました。著者はカナダ在住ですが、本書の主人公と同じくアフリカ生まれ、アフリカ育ちのインド系人種だそうです。カナダでの評価は高く、カナダの代表的な文学賞であるギラー賞を二度受賞した二人のうちの一人です。もう一人は、昨年、ノーベル文学賞を受賞したアリス・マンローです。イギリスの植民地であったケニア の独立前後を扱った本書は、帯には、「アフリカでもっとも汚職にまみれた狡猾な詐欺師、ヴィクラム・ラル」と書かれて、なにやらキナ臭いのですが―実際、本書の内容は相当にキナ臭いし、暴力的、陰謀的、非情、狡猾なのですが―、主人公の独白である本書は、瑞々しい初恋、友情、兄妹愛、家族愛、実らぬ悲恋、すれ違う想い、凍りついたこころ、悲劇、安らぎ、寂寥、諦念に満ちて、美しくも悲しいものです。主人公は言い訳をしているのかも知れませんが、そのこころはやわらかく、傷つきやすく、悲しみに満ちています。幼い友人一家(そこには淡い初恋の相手も含まれていたのですが)を惨殺した暴力は、小さな主人公にはあまりにも大きな衝撃であって、彼は、その時点で人生のすべてを諦めてしまったのかも知れません。イギリス人でもアフリカ人でもないインド系ケニア人は、狭間に生きる、つまりは、生きる場所の無い、狭間の悲しい運命を生きるしかなかったのかも知れません。情感豊かな感性を瑞々しく描ききった本書は、オルハン・パムクの「雪」を彷彿とさせる名著でした。 パオロ・ジョルダーニョの最新作「兵士たちの肉体」を読みました。同じ作家を続けて読むことは、異例なことです。アフガニスタンに派遣されたイタリアの兵士たちを描いたこの作品は、「プラトーン」のような、安易な気持ちで兵役に参加してみたらとんでもない地獄を見た、みたいな作品かなと思って読み始めたのですが、「素数たちの孤独」同様に、この作家には肩透かしを食らわされました。緊張状態を冷静に保ち、肉体が理性を凌駕する戦地という特殊環境におかれた、若者たちを描いたこの作家の意図は、戦争という異常事態を 描くことではなく、それぞれに自分でどうにもならない弱さを抱え込んだ若者たちを、魅力的に(ということは、つまり、どうにもならない弱さを抱え込んだ生こそが、どこにでもいる普通の人間の運命なのだ、と言いたいのかも知れません)描いてみせました。テーマとしては、「家族とは何か?」、「戦争はなぜ起きるのか?」、「ひとはどうやって兵士になるのか?」というようなことが、疑問ではあるのでしょうが、それは、単なる状況の示す疑問であって、本当は、苛酷な異常事態(非日常)のあからさまにする、人間の弱さこそが、人間の共通して乗り越えなくてはならない、「普通の人生」なのだと言っているように思えてなりませんでした。この歳になると、誰だってそれぞれに大変な問題や苛酷な人生を、なんとはなしの日常にまぎらせながら生きているのだ、誰にも、人には言えないような苦労はあるんだ、と、物知り顔で言いたくなるのですが、それは、万国共通なようです。「生きる悲しみ」、「人生はなんと悲しいものか」なんて、誰もが等しく感じる感慨です。その意味では、この若い30代前半の作家の示す人生は、確かに苛酷ではありますが、取り立てて騒ぐほどのことはない、万人の感じる感慨ではあるのです。ちょっと、年寄りめいた言いように過ぎる感想ではありますが・・・・・・! どうにもならない弱さを、人間の属性として肯定する態度は、私もおおいに同感です。勝ち組や強い人間にたいする、陳腐さや興ざめを感じる感性は、私の負け犬根性でしょうか!? 題名に魅かれたのでしょう。「素数たちの孤独」は、イタリアの文学賞の最高峰の一つストレーガ賞を2008年、26歳の最年少で受賞 した素粒子物理学者パオロ・ジョルダーノの処女作品です。「奇跡の恋愛小説」という本の帯は、邪魔でしかなかったですね、結果的には……。幼少期の記述のある小説は、ある意味で未成熟な陳腐さを感じてしまいます。なんだか、説明的過ぎて……。だから、主人公の「孤独な素数」たちは、きっと結ばれるに違いないという、安っぽい結末を予想していたのです。その期待は、見事に裏切られて、小説は救いの無い物語に変貌し、その文学的な深みは、結果的に深くなりました。ある苦しみから逃れられない人間は、どうやって生き続けていけばいいのだろうか、という作者の、読者への投げかけは、作品の中では答えを見いだせないからこそ 、その作品は陳腐さから逃れられるのでしょう。この作者の最新長編、「兵士たちの肉体」を、挑戦し続ける気持ちで、読んでみようと思います。 トニ・モリスンは初めてだった。彼女は、アフリカン・アメリカンの女性作家として初のノーベル文学賞を1993年に授与されている。「ホーム」は中編と呼んでもよいような第十長編になるらしい。私が読み落としたのかも知れないが、読んでいる間ずっとこれは二グロのお話だよな、と思いながら読んだ。その感触は間違いではなかった。見えてきたのは、希望。凄まじく、過酷なお話であるが、愛する者や、安心して暮らせる場所があれば、それが、すなわち「ホーム」なんだけれど、人は優しくもなれるし、なんとか生き抜くことだってできる。ニグロスピリチュアルのように、「ホーム」は神の懐にしか 無いとは、言わない。どこにだって、捜せば、「ホーム」はどこにだって、見つけられる。そのキーを握っているのは、どうやら、女性の逞しさや、連帯や、共同生活や、楽観主義のなかに棲んでいるらしい。人は誰だって、優しく満ち足りた生活ができるのではないかという、希望の膨らんだ作品だった。いつか彼女の代表作である「「ビラヴド」も読んでみたくなった。 村上春樹が自作一篇を含めて10の短編ラブストーリを翻訳したものです。アリス・マンローの「ジャック・ランダ・ホテル」は、私が村上作品以外に唯一読んだことのある作家の作品でしたが、さすがに読み応えのある「上級者(村上言)」向けの大人の恋のお話でした。なかで、一番よかったのは1978年生まれで、夫と二人の息子とフロリダに住む女性作家、ローレン・グロウの「L・デバートとアリエット―愛の物語」でした。「短編なのに、大河ドラマを思わせるような歴史小説仕立て」と村上春樹も評するように、引き裂かれた恋人たちが、お互いに世に名を成していく様を、陰からそっと、しかし万感の思い入れをもって注目し続ける現実は、悲しくも感動的でした。恋人の父親に睾丸を抜かれ不具者となった詩人を、マネージャーとして生涯支える恋人との間の一粒種の息子。その様子を、そっと見守るオリンピック水泳で活躍する恋人(母親)。第一次大戦末期の「オリンピックの水泳」と「スペイン風邪」という史実を絡ませたのが、リアルでした。それにしても、アリス・マンローがノーベル文学賞を獲ったと知ったとしても、村上春樹はこの短編集にアリス・マンローを加えていただろうかと、げすな勘繰りをするのは私だけでしょうか? だって、アリス・マンローは作品の数が足りずに、柴田元幸先生に勧められて、確かに面白いといって加えた作品だったのだそうですから。 米国のポール・オースターは、私が、柴田元幸先生の翻訳で ずっと読み続けている作家です。本年1月発行の最新作(と言っても米国での出版は2006年です。お忙しい柴田先生ですから、このタイムラグは致し方ありません)「写字室の旅」を読み始めたとき、あまり進まなかったのは、前に読んだ「HHhH」があまりに圧倒的な印象を残していたからでした。歴史的実話の力です! あらかたの記憶を失くして幽閉されている老人を次々に訪れる人々は、かつてオースターの作品に登場した名前をもった人々だったのだそうです。私は、記憶していませんでした。老人はかつて多くの人に過酷な任務を課して、その任務を負わされた人々が老人のもとを訪れているらしいのです。老人は消し難い罪悪感をその人々に感じるのですが、自分がかつてその人々に犯してしまった罪すら記憶が無いのです。オースターらしい、寓意を含んだからくりのあるお話ですが、どうも、実験小説でも読んでいるような感じで終わってしまいました。次の「闇の中の男」との連作として読むと、「戦争」という大きなテーマが浮かび上がってくると、柴田先生が解説されていますから、次回作の出版を心待ちにしておきましょう。 ローラン・ビネというフランス生まれの若い作家の「HHhH(エイチエイチエイチエイチ)プラハ、1942年」という本を読みました。これは、掛け値なしに最近の数年で読んだ本の中で一番感動した本のうちの一冊です。ガルシア=マルケスの「百年の孤独」 を読み終えたときに感じた感動(内容的にはどちらのお話も悲劇的で茫然としたのですが)に匹敵する充足感を覚えました。この本の前に読んだ本はノーベル賞をとったユダヤ人作家のものでしたが、この本の悪役(この本は史実ですから、悪役というのは一方的な言い方過ぎるかもしれませんが)はホロコーストでユダヤ人を大量に虐殺したドイツナチスの高官、ハイドリヒだったというのは読み始めた分かった皮肉な巡り合わせでした。綿密で膨大な資料から、作者はできる限り史実を述べようとするのですが、「小説とは何か?」、「フィクションとは何か?」、「史実とは何か?」と随所で自らに問いかけながら、しかし、この作家の出自がそうさせるのでしょう、ナチスや現在の母国フランスにさえ並々ならぬ恨みや怒りを秘めながら、史実は淡々と進行し、やがて、思いもよらぬ歴史の大きな歯車が回り始めるのです。チェコスロバキヤの人々が英雄と尊敬する数人の兵士(主には二人)は、ナチスの歴史を塗り替えるような偉業を達成します。ただし、大きな犠牲を払うことになります。それは、事実であるがゆえに圧倒的な迫力で読者に迫ってきます。「ル・モンド」、「ニューヨ-カー」、「タイムズ」などの各誌やノーベル賞作家、マリオ・バルガス・リョサなどの絶賛を浴びて、栄えある文学賞も受賞したのです。ちなみに「HHhH」というのはHimmlers Hirn heinsst Heydrich(ヒムラーの頭脳はハイドリヒと呼ばれる)の頭文字を並べたものです。ハイドリヒは「ドイツでもっとも危険な男」「金髪の野獣」と呼ばれて恐れられた冷徹なホロコーストの首謀者だったのです。しかし、主人公と呼ぶべきは、もちろんそのハイドリヒに挑む、チェコとスロバキアの勇敢な青年兵士であります。 アイザック・バシュヴィス・ジンガーという1904年(異説では1902年とか)にポーランドで生まれたユダヤ人作家の「不浄の血」を読みました。この作家は1978年にノーベル賞を受けています。近代化に乗り遅れた東欧のユダヤ人集落を舞台にした軽妙な小噺風の短編に定評があるそうですが、この本にもたくさんのそのような短編が紹介されています。その短編はドイツ賤民研究で有名な阿部謹也先生の収集されたティル・オイレンシュピーゲル(リヒャルト・シュトラウスにも取り上げた曲があります)のとんち話を彷彿とさせるような味わいがありました。 ティル・オイレンシュピーゲルはドイツの昔話の民衆本に登場してくるとんち男のことです。道化であったり、手品師だったり、職人や農民だったりします。こちらのほうがずっとプリミティブですが……。アイザック・バシュヴィス・ジンガーという作家はイディッシュ語(ヘブライ・ドイツ語)で作品を書いた作家だそうです。ユダヤの民衆と母国語(?)を愛しながら、米国に亡命したようです。この本のなかでは「おいらくの恋」というのが逸品でした。訳者の西成彦先生の解説では、「妄想の力こそが、ひとの生を下から支え、ひとの性欲や感情をぐいぐい引っぱり、突き動かしているという現実を、われわれは直視しなければならない。バシュヴィス・ジンガーの偉大さは、幻想や妄想こそが『現実的=リアル』だということを徹底的に描くことのできた、たぐいまれな20世紀作家のひとりだった」と評されていますが、バシュヴィス・ジンガー自身も「わたしは奇怪な話を書くのが好きで、死にゆく言葉こそがふさわしい。言葉が死んでゆくにつれて、奇怪なものはますます生き生きとしてくるのです」と語ったそうです。彼は、ノーベル賞の受賞の折に、イディッシュ語が晴れて世界に認知されたことを喜んだそうですが、一方で「国土も国境も持たない、孤立無援の故郷喪失者の言語」とも語ったそうです。イディッシュ語には、「武器」や「弾薬」や「軍事演習」や「作戦」をあらわす単語はないのだそうです。彼の愛する同朋たちが、おぞましいホロコーストの悪夢に巻き込まれて行くことは、誰もが知る、悲しい出来事です。米国に亡命できたバシュヴィス・ジンガーが、胸の引き裂かれるような思いでその悪夢を眺めていたことは想像に難くありません。彼は、その悪夢が過去のものとして去ったのちもイディッシュ語で作品を書き続けたのです。 末井 昭さんの「自殺」を読みました。赤裸々な末井さんの半生の伝記であるとともに、自殺することのあほらしさを訴えているのです。自殺を考えるような人は、まじめで優しい人たちなのだと、そんな人たちが死んでしまったら、自殺する人のことを競争社会の「負け組」だと片づけるような鈍感な人間ばかりがはびこって、悲惨な社会になってしまうから、自殺なんて止めてくださいと訴えている、自殺ストップという本なのです。B級人間を自称するような末井さんの優しさと逞しさと、そして、クリスチャンに行き着いた末井さんの悟りの書のようにも思えました。B級人間なんて誰が決めるんだろう。「どのような状況であれ、窓を開けた時にふっと入り込んできた小さな風に気持ち良さを感じられることができれば、その人の人生、勝ちである」という永沢光雄のことばの引用がとても印象的でした。 イタリア在住のジャーナリスト内田洋子さんの「ジーノの家」を読みました。この人の新作「ミラノの太陽、シチリアの月」を読んで面白かったので、二冊目として本書を手に取ったのですが、この本、史上初の日本エッセイスト・クラブ賞と講談社エッセイ賞のダブル受賞作品でした。だからといって選んだわけではありませんが。確かに、大人のほろ苦いドラマを演じながらイタリアの市井に生きる人々を描いた渋い作品で、ダブル受賞もさもありなんという説得力がありました。内田さんが危ないイタリアで逞しくなられていく感じも共感できました。熟した生、性の香りもぷんぷんしました。文春文庫の解説では内田さんが遠慮がちに作品に登場していると書いてありましたが、私には大人、内田洋子のプライベートな生態も垣間見えるようなきわどい香りも感じたのですが、深読みだったのでしょうか。それにしても、最後の作品など、職人の頑固さ、実直さ、優しさ、無口さは洋の東西を問わないのだと思い知らされ、人生の機微までジンと沁みるほろ苦い秀作でした。 今日、平成25年10月10日、今年のノーベル文学賞を村上春樹がまた逸したといって騒いでいるようですが、村上春樹ファンの私としても、村上春樹はノーベル賞を獲るには、世界中で万民受けし過ぎていると思うのです。これだけ、万民に読まれ、この上もない賞賛を受けている人間がノーベル文学賞まで獲ってしまったら、世の中とはなんと不公平なものかと、私などは失望を禁じ得ません。そして、今年のノーベル文学賞はカナダの短編作家として定評のあるアリス・マンローに授与されることになったそうな。アリス・マンローは確かに短編らしい短編をものする作家だと思いますが、この方もさんざん賞賛され尽くして、今年、まさに作家業を引退すると宣言したところに転がり込んだノーベル賞も、出来すぎといえば出来すぎではありますよね。上手い短編だけれど、メッセージ性の低い作家だとは思うのです。 V.S.ラマチャンドランという神経科学者の書いた「脳のなかの天使」を読みました。この研究者は以前「脳のなかの幽霊」という本で有名になって、この本はその続編という訳です。人類700万年の歴史の中で7万年から6万年前ころに突然の爆発的な精神の向上が起こり、「大躍進」と呼ばれています。この本は、そのような芸術や言語、装飾、抽象的思考、自己認識などという特殊な文化を持つ人間がいかにしてそのような特別な生物となったのかを、脳科学の面から洞察しています。カリフォルニア大学サンディエゴ校の脳認知センター教授および所長という、このサイエンティストの発想は柔軟、大胆で、しかもシンプルな患者さんの観察やちょっとした実験から、驚くような事実を明らかにしてくれます。人類の「大躍進」は脳の機能がその時に偶然爆発的に一気に進化したのではなく、ほかの類人猿とは違った脳進化の積み重ねが、ちょうどそのときもう後戻りのできないカスケードの堰を切ったように溢れ出始めたといいます。それは、今日のインターネットやウキペディアやブログと同じで、一度遭遇したらもうそれ失くしては日常が進まなくなったのに似てるといいます。遠い遠い我々の祖先がそのときの生活に適するように特定の脳の部分を発達させて(実は逆で、そのように発達した脳をもった人類がその環境に適して生き残ったということなのでしょうが)、その脳の場所場所が複雑にやり取りのためのネットワークを創ると、当初の目的からは想像もできなかったことができるようになっていったのです。最初は単純なお話だったに違いありません。それが、こともあろうに美や芸術を感じ、自己と他者を認識する自意識をもった、「ただの類人猿」を遥かに凌ぐ、地球の主人公たる哺乳類となったのです。 オルハン・パムクはわたしの好きな作家のひとりです。彼の傑作のひとつである「雪(原題KAR)」を読みました。複雑な中東の政治や宗教の扱われたこの作品は、彼の唯一の政治小説なのだそうですが、しかも、この作品がアメリカの同時多発テロの翌年に上梓されて世界的に反響があったそうな……。そのような硬いテーマをモチーフにしながら、わたしには、主人公のKaと呼ばれる詩人やその足跡を綴る作者と同一人物であろうオルハンという小説家たちの、ひ弱さや恋に望を託すロマンチシズムの悲しみばかりがこころに沁みた作品でした。Kaもオルハンもよく泣いています。弱いからこそ惹かれてしまう人間の一面を思わずにはおられなかった傑作でした。「生きる悲しみ」を降りやまぬ雪に重ね合わせてしまうのは、わたしばかりでしょうか? わたしは、ここのところ、外国の作家の作品を読むことが多いのですが、村上春樹は新刊が出ればたいてい買って読み続けている数少ない日本人作家の一人です。勿論、最新刊(2013年)も買って読みましたが、この作品、発売から一週間で100万部売れたとか! 好ましいことではありません。だって、100万部といえば、日本人の100人に一人、でも、小さな子供やずっと年配の方は読まれないことが多いでしょうから、何人に一人が、この作品を手にしたかを想像すると、気色が悪くなります。村上春樹ファンを口にすることが憚られる状況で、大変危惧しています。だって、村上作品を読むということは、十人並みのつまらない読書をしていることを宣言するようなものかもしれませんからね。作家にとってもこんな過熱したブームは迷惑な話に違いありません。じぶんが陳腐化していることを、突きつけられているようなものですから。ノーベル賞候補に名前があがっても、こんな大衆に受け入れられるアイドルや教祖のような作家に、わたしが選考委員なら、賞を与える必要性など考えられもしません。村上春樹にとってはいい迷惑かも知れないとさえ思ったりします。作品はそれなりの読み応えはありましたが、この作家は、大衆に受け入れられる、素直で、率直で、ファッショナブルで、読者のツボを押さえすぎているような感想をもちました。彼はジャズやクラッシック音楽に造詣が深すぎて、あまりに洗練されすぎているいると、今回の作品でも感じました。ただ、一点、この作品を読んで救われる人は多いように思いました。それが、村上作品が多くのファンをひき付けてやまないもっとも大きな理由であるのかも知れません。 |